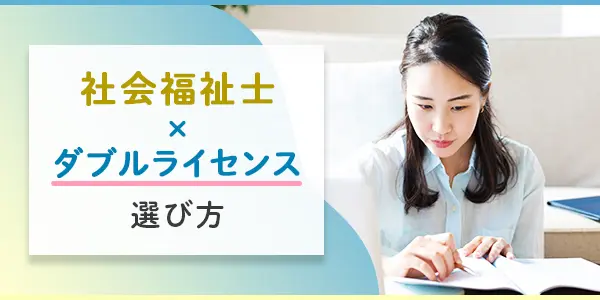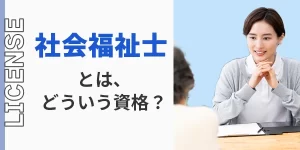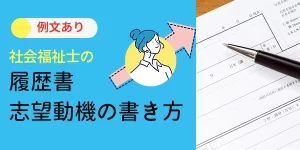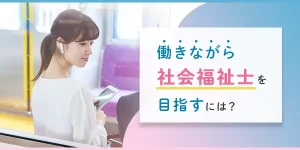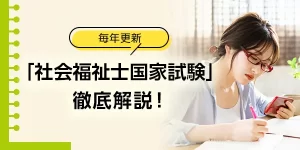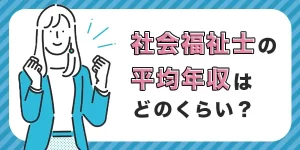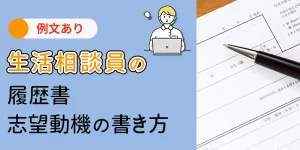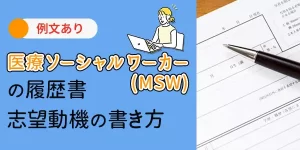社会福祉士が対象とするのは高齢者・障がい者・児童など様々。働いている場所も福祉施設や医療機関、公的機関など多岐にわたっています。
そのため求められる知識や連携先も幅広く、常に研鑽が必要となります。
ダブルライセンスを取得することは、知識を増やし、より幅広い事例に対応できるとともに、他の分野への転職の選択肢も増えることでしょう。
ケアマネ・相談員
障がい福祉資格専門!
完全無料の転職エージェント
ご相談ください。
- 自分では良い求人を
判断できない… - 今より給料アップ
したい! - 自分に合う職場
を探してほしい
目次
ダブルライセンスの選び方のポイント
関連分野の資格を選ぶ
自分が現在働いている領域によって、活用できる資格は変わります。
現在の領域の関連分野の資格を選ぶと良いでしょう。
たとえば以下のような資格があります。
- ケアマネジャー
- 介護福祉士 など
- 精神保健福祉士 など
- 保育士 など
現在働いている分野の関連資格を取得することで知識を深め、より多様なニーズに応えることができます。
自分のキャリア目標に合わせた資格を選ぶ
他の分野や職種への転職を考えている場合は、進みたいと思っている分野の資格を取得することで転職の可能性も広がります。
また、障がい分野で働く場合、以下の資格を取得することで業務の幅が広がり、職場内でのキャリアアップも可能です。
- サービス管理責任者
- 相談支援専門員 など
社会福祉士としての専門性をより高めたい場合は、以下の上位資格もあります。
- 認定社会福祉士
- 認定上級社会福祉士
要件を満たし、職能団体が実施する研修を受講することが必要です。
上位資格を取得することで、さまざまなニーズに対応するスペシャリストを目指せます。
需要が高い資格を見極める
高齢化がすすみ、介護や福祉に関する資格の需要はますます高まっています。
社会の動向や需要に応じたキャリアアップを考えていくことも重要です。
また、働いている地域によってもニーズは異なります。
該当地域で需要の高い資格についても確認しておきましょう。
自分の強みを生かせる資格を選ぶ
自分の長所や強みを把握し、それに合った資格を選ぶ方法もあります。
たとえば、体を動かすのが好きであればリハビリ系の資格を目指すなどです。
これまでのキャリアで得た知識や経験を活かす方法もあります。
例)地域包括支援センターで働いてきて、成年後見制度には詳しいといった場合下記の資格を取得することで後見人業務に役立てることもできます。
- ファイナンシャルプランナー
- 宅建 など
社会福祉士におすすめのダブルライセンス8選
精神保健福祉士(メンタルヘルス支援の専門職として活躍)
精神保健福祉士は、精神疾患や精神障がいのある方が社会生活を送れるよう相談支援を行う国家資格です。
既に社会福祉士を取得している場合、国家試験の共通科目が免除になるのも魅力です。
社会福祉士資格保持者が精神保健福祉士の資格を取得するには、専門の養成校などで指定単位を取得後、国家試験に合格する必要があります。
受験資格の詳細については公益財団法人社会福祉振興・試験センター試験センターでご確認ください。
- 精神科病院やメンタルクリニック(病院のソーシャルワーカーやデイケア)
- 地域の障がい者支援施設(地域活動支援センターや就労支援施設、グループホームなど)
- 相談支援事業所
- 行政機関(保健センターやこころの健康センターなど)
- 企業(従業員へのメンタルヘルスサービスの提供など)
介護福祉士(高齢者介護と連携したサポートが可能)
介護福祉士は、高齢者や障がい者の食事、入浴、排せつなどの介助を行う専門職です。
社会福祉士が主に相談業務や福祉制度を利用した環境調整をするのに対し、介護福祉士は直接高齢者や障がい者の身体の介助を行うのが特徴です。
施設で相談員として働いている場合は、身体介護の知識を身に付けることで、「介護現場を知っている相談員」という信頼を得られます。
また、介護を必要とする対象者の身体状況を正確に把握することにも役立ちます。
自宅で高齢者を介護するご家族に対しても具体的な介護技術を助言できるため、地域を舞台に活躍できるでしょう。
国家試験の受験資格は介護職としての実務経験(3年以上)を積んだのち実務者研修を受講し、国家試験に合格するか、指定された養成施設に通う必要があります。
受験資格の詳細については公益財団法人社会福祉振興・試験センター試験センターでご確認ください。
- 高齢者施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、デイサービス、グループホームなど)
- 障がい者支援施設(入所施設や通所介護施設、グループホームなど)
- 訪問介護事業所
ケアマネジャー(介護保険サービスを調整し、高齢者の生活を支える専門職)
ケアマネジャーは、介護保険サービスの利用を希望する高齢者やご家族の希望を聞き、自立した生活を送れるようサービス利用の計画を立て、マネジメントを行う相談員です。
国家資格ではなく、都道府県が主体となって認定している公的資格で、受験するには保健・医療・福祉に関する法定資格取得後5年の実務経験が必要となります。
高齢者施設のほか、地域の居宅介護支援事業所で働くことができます。
また地域の高齢者の総合相談を受ける地域包括支援センターでは、社会福祉士、保健師とともに主任ケアマネジャーが必置となっています。
ケアプラン作成についての知識を得ることで、実際に介護に関する相談援助を行う際に、具体的な助言ができ、多職種との連携にも役立ちます。
| 受験対象者 | 必要実務経験 |
|---|---|
| 法定資格 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士 | 通算実務経験年数が5年以上かつ、当該業務に従事した日数が900日以上 |
| 相談援助業務に従事する者 ※詳細は主催元及び県のHP、申し込み資料でご確認ください。 |
参照:ケア人材バンクHP(【2024年度】第27回ケアマネジャー試験の受験資格、申込方法、受験対策まで詳しく解説! | 【ケア人材バンク】【公式】)
- 居宅介護支援事業所
- 高齢者施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、デイサービス、グループホームなど)
- 訪問介護事業所
- 地域包括支援センター
理学療法士(身体機能の改善を支援するスキルを習得)
理学療法士は、病気やけがなど様々な事由で身体機能が低下した人を対象に、運動機能の回復のためのリハビリテーションを行う専門職です。
介護保険の導入に伴い、介護分野での需要も高く、住宅改修や福祉用具の相談、医療と介護サービスの連携、介護予防など、あらゆる場面で活躍できます。
専門の養成学校に通い、国家試験に合格する必要があります。受験資格の詳細については厚生労働省でご確認ください。
- 医療機関(一般病院など)
- 高齢者施設(特別養護老人ホームや介護老人保健施設、デイサービス、デイケアなど)
- 障がい者施設(身体障がい者療護施設、身体障がい者福祉センターなど)
- 児童福祉施設(肢体不自由児施設、重症心身障がい児施設、知的障がい児通園施設など)
- 訪問リハビリテーション事業所や訪問看護事業所など
作業療法士(リハビリテーションの専門知識で支援の幅を広げる)
作業療法士は、心身に障がいのある人を対象に手芸や余暇活動など様々な作業をとおして、食事や着替えなどの応用的な動作ができるよう指導や援助をするリハビリテーションの専門職です。
リハビリテーション病院のほか、精神科病院でも活躍しているのが特徴です。
専門の養成学校に通い、国家試験に合格する必要があります。受験資格の詳細については厚生労働省でご確認ください。
- 医療機関(一般病院、精神科病院など)
- 高齢者施設(特別養護老人ホームや、介護老人保健施設、デイサービス、デイケアなど)
- 障がい者施設(地域活動支援センターや就労支援施設など)
- 児童福祉施設(障がい児入所施設、知的障がい児通園施設など)
- 訪問リハビリテーション事業所や訪問看護事業所など
言語聴覚士(コミュニケーション支援を行う専門職)
言語聴覚士は、病気や先天性の事由などにより言葉や聞こえ、食べることに障がいのある人を対象に、その原因を探り、発語や嚥下などの訓練を行うリハビリテーションの専門職です。
脳疾患や認知症、嚥下などは、介護予防の観点からも注目されています。
医療機関や福祉施設、障がいのある児童の療育施設などで働き、子どもから高齢者まで幅広くリハビリの対象としています。
専門の養成学校に通い、国家試験に合格する必要があります。詳しくは厚生労働省ホームページでご確認ください。
- 医療機関(一般病院など)
- 高齢者施設(特別養護老人ホームや介護老人保健施設、デイサービス、デイケアなど)
- 障がい者施設(地域活動支援センターや就労支援施設など)
- 児童福祉施設(重症心身障がい児施設、知的障がい児通園施設など)
- 教育機関(特別支援学校や保育所、幼稚園など)
- 訪問リハビリテーション事業所や訪問看護事業所など
保育士(児童福祉分野への展開)
保育士は乳幼児を対象に健全な成長と発達を支援する専門職です。
活躍の場は多岐にわたり、保育所のほかに障がい児施設や放課後等デイサービス、児童養護施設や児童相談所などでも働いています。
養成校に通うか実務経験を積めば資格取得できますが、概ね短大卒以上の学歴があれば誰でも保育士国家試験を受験することができるため、働きながら資格取得がしやすいことも魅力です。
保育士の受験資格については一般社団法人全国保育士養成協議会にてご確認ください。
- 保育所・認定こども園
- 児童養護施設
- 病児保育施設
- 児童館・学童施設
- 地域子育て支援センター
- 障がい児施設(障がい児通所支援施設、放課後等デイサービス、療育センター、重度障がい児施設)
- 行政機関(児童相談所、子ども家庭センターなど)
ダブルライセンスを活用したキャリアアップのメリット
医療・福祉・教育分野での高い専門性を発揮
社会福祉士として積んできた経験に加え、新たにダブルライセンスを取得することで、高い専門性を発揮できます。
地域には複合的な課題を抱えた方も多くいらっしゃいます。
高齢者を対象にした仕事であっても、同居のご家族に精神疾患があるといった事例は少なくありません。
そのような時に幅広い知識を持っていることで、質の高い支援が可能になります。
様々な専門知識を得ることで、関係機関との連携も円滑になり、対象者本人やご家族からも信頼を得ることができます。
働く現場での具体的な活用事例
ダブルライセンスの具体的な活用事例を働く現場ごとに確認しましょう。
地域包括支援センターでは、社会福祉士とともに主任ケアマネジャーも必置資格となっています。
社会福祉士は主に権利擁護や総合相談を担っていますが、主任ケアマネジャーの資格を取ることで、ケアマネジャー支援についての見識も広げることができます。
医療ソーシャルワーカーは疾患の知識や医療機関のしくみ、コメディカルとの連携に長けた存在と言えます。
精神保健福祉士資格を取得することで、一般病院だけではなく精神科病院でのソーシャルワーカーの道も開けるなどキャリアアップにつながります。
児童分野で働く場合、保育士資格を取得することで子どもの発達や関わり方についての知識を深めることができます。
また、保育所においては、複雑な課題を抱える家庭もあります。そうした時に保育とソーシャルワークの双方の視点からアプローチできると強みになります。
資格を活かした職場選びと転職が可能
昨今の社会福祉はニーズが多様化し、制度も日々変わっています。
ダブルライセンスを取得することで、社会の課題や需要が変わった場合にも、転職を含めた柔軟なキャリア形成が可能です。
たとえば社会福祉士が精神保健福祉士を取得することで、精神科病院や保健センター、産業保健分野など、職場選びの選択肢が増えることになります。
独立の可能性が広がる
最近では独立型社会福祉士という働き方も注目されています。
組織に雇用されるのではなく、自身で事業所を構え、対象者の福祉に関する相談にのっています。
しかし、相談援助業務のみで運営していくには収入が安定しないため、多くの事業所は成年後見人の受任や介護保険のケアプラン作成、介護保険外の自費サービス業、福祉事業者へのコンサル業務などで収入を得ていることが多いようです。
そのため、ケアマネジャーの資格を得ておくことや成年後見人活動に役立つ資格を取得しておくことは独立を考えている場合に大きく役立ちます。
ダブルライセンス取得までのプロセス
資格取得に必要な学習方法と時間管理
限られた時間の中で学習するには学習計画と時間管理が重要となります。
いずれの資格取得においても過去問を繰り返し解くことが最短で効率的な勉強法となります。
国家試験の過去問アプリなども充実しており、隙間時間に過去問の学習を行うこともできるので、上手に活用しましょう。
養成校などに通っている場合は学校で試験対策を行っている場合もあります。
また職能団体で国家試験対策などを行っている場合もあるので上手に活用しましょう。
働きながら資格を取得するには
働きながらの資格取得の、何より時間管理が求められます。
目標設定となりたい自分のビジョンを持つこと、目的を忘れないことが重要です。
家族や同僚の協力が得られるかも大切です。
学習する仲間を見つけることもモチベーションに大きく影響します。
最近ではSNSなどでも資格取得を目指した人とつながることができますので、情報交換しながら効率的に資格を取得しましょう。
何より体調管理に気を付けましょう。
継続的なスキルアップの重要性
急速に進む少子高齢化や社会情勢の変化などに伴い、社会福祉制度はめまぐるしく変わります。日々新たな情報を得て知識をブラッシュアップすることが大切です。
また最近では多職種連携も重要視されています。
関係する支援機関が、互いの専門分野について知ることで、より円滑な連携につながり、ひいては対象者の役に立ちます。
資格取得に限らず、研修やセミナーなども活用し、支援技術の向上を目指しましょう。
まとめ
社会福祉士の支援対象は幅広く、横断的な知識が求められる資格です。
ダブルライセンスを取得することで、支援の質を高めるとともに、キャリアプランの選択肢も増えます。
ぜひ今後自身がどのようにキャリアアップしていきたいかを考え、資格取得をひとつの手段として向上していきましょう。
ケア人材バンクでは、社会福祉士や相談員専門の転職エージェントが多数在籍しており、転職活動をサポートしています。
キャリアプランを含めたご相談もお受けしていますので、ぜひ登録の上、お気軽にご相談ください。登録は無料です。
※当記事については、各自治体の情報を参考に作成しておりますが、最新情報は必ず関係機関のHPをご確認ください。
※当サイトで提供される情報は、一般的な情報提供のみを目的としており、専門家による助言に代わるものではありません。特定の状況に関するアドバイスや支援が必要な場合は、必ず専門家にご相談ください。