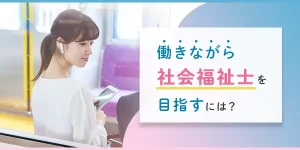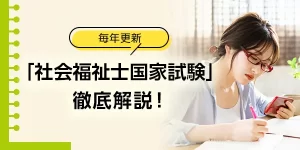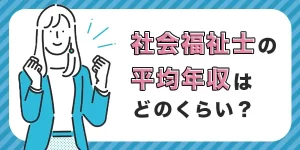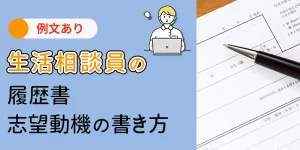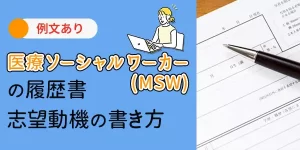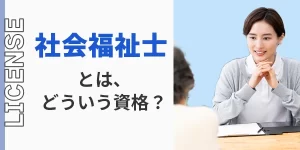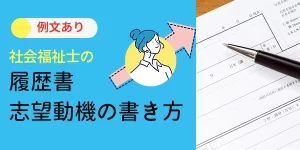地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口として地域の中核を担う重要な機関で、社会福祉士の配置義務があります。
そこで働く社会福祉士には、高齢者の権利擁護や総合相談支援など、専門性の高い業務が求められます。
社会福祉士として転職先を探す際に、地域包括支援センターを検討することもあるでしょう。
そこで本記事では、地域包括支援センターで働く社会福祉士の役割や業務内容、必要なスキル、キャリアの展望まで詳しく解説していきます。
目次
地域包括支援センターで働く社会福祉士の役割とは?
地域包括支援センターは、社会福祉士が専門性を発揮できる職場のひとつです。
ここでは、地域包括支援センターの機能と社会福祉士の役割について解説します。
地域包括支援センターとは何か?
地域包括支援センターは、地域に住む高齢者の暮らしをサポートするための公的な相談窓口です。
市区町村が設置主体となり、社会福祉士・主任介護支援専門員、保健師などの専門職を配置し、高齢者やそのご家族、地域住民からのさまざまな相談に対応しています。
令和6年4月末現在、全国に5,451か所設置されており、おおむね中学校区に1か所(圏域人口2〜3万人)を目安の設置となっています。
出典:厚生労働省「地域包括支援センターについて」
地域包括支援センターが行う主な業務は、以下の4つです。
- 総合相談支援事業
高齢者やご家族からの相談を受け、適切なサービスや制度利用へつなげる - 権利擁護業務
高齢者虐待の防止や成年後見制度の利用支援など、高齢者の権利を守る業務 - 介護予防ケアマネジメント
要支援1・2の方のケアマネジメント業務 - 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
地域のケアマネジャーへの支援や関係機関とのネットワークづくり
2025年以降、団塊の世代が75歳以上となり、国民の5人に1人が後期高齢者となります。
これにともない、従来の介護サービスだけでは高齢者の生活を支えきれなくなるおそれがあります。
その対策として、国は「地域包括ケアシステム」の構築を推進しており、地域包括支援センターはその中核を担う機関として重要な役割を担っています。
社会福祉士が果たす重要な役割とは?
地域包括支援センターにおける社会福祉士は、高齢者とそのご家族が抱える生活上の課題を整理し、適切な支援へつなげる重要な役割を担います。
寄せられる相談は、ADLや認知機能の低下、貧困など、複雑な背景を持つことが多いです。
また、虐待やヤングケアラー、介護離職といった家庭の問題に対応することも少なくありません。
社会福祉士は、高齢者福祉の他にも、障がい者福祉、社会保障制度など、福祉全般に関する専門知識と相談援助技術が必要です。
これらを活用し、多角的な視点から問題解決に取り組みます。
具体的には、高齢者虐待対応、成年後見制度利用支援、消費者被害防止など、権利擁護に関する業務が中心です。
さらに、主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)や保健師などの専門職、地域の医療機関や介護サービス事業所、民生委員やボランティア団体など、多職種・関係機関と連携し、包括的な支援体制を構築することも重要な役割です。
社会福祉士が地域包括支援センターで担当する主な業務内容を解説
地域包括支援センターにおいて社会福祉士は、総合相談支援業務や権利擁護業の中心的な役割を担います。
ここでは、社会福祉士が地域包括支援センターで実際に担当するケースの具体例や、介護予防ケアマネジメントについて解説します。
社会福祉士が行う相談業務の具体例
地域包括支援センターにおける社会福祉士の相談業務は、関係機関との連絡調整や窓口・電話での相談対応、安否確認のためのご利用者宅訪問といった業務です。
具体的には、以下のとおりです。
- 経済的に困窮している高齢者に対して、生活保護制度や各種貸付制度の利用の提案、申請手続きのサポートなど
- 判断能力が低下している高齢者に対して、成年後見制度活用の検討、関係機関と連携、手続きのサポートなど
- 虐待の早期発見・対応のため、関係機関への通報や緊急介入、継続的な見守りなど
また、高齢者本人だけでなく、介護を担うご家族への支援も重要な役割です。
ご家族全体の状況を把握したうえで、包括的な支援を行います。
- 介護疲れのような介護に対する悩みの聞き取り
- 介護保険サービスの情報提供
- 介護方法のアドバイス
- 休息のためのレスパイトケアの提案
このように、社会福祉士は、相談者との信頼関係を構築しながら、専門的な知識と多角的な視点、そして関係機関との連携を通じて、高齢者とそのご家族が地域で安心して暮らせるよう支援します。
介護予防ケアマネジメントの流れと実践
地域包括支援センターにおける介護予防ケアマネジメントは、主に保健師が中心となって行う業務です。
社会福祉士は、生活課題の把握や権利擁護の視点から、チームの一員としてこの業務をサポートします。
介護予防ケアマネジメントは、要支援1・2の認定を受けた方や事業対象者に対して行われ、その流れは以下のとおりです。
| アセスメント | ・心身の状態や生活環境の評価 ・自立支援に向けた課題を把握。 ・社会福祉士は経済状況や権利擁護の必要性などについて専門的な視点を提供。 |
| ケアプラン原案作成 | ・本人の意向と課題を踏まえ、具体的な目標とサービス内容を設定。 ・社会福祉士は地域の社会資源に関する情報を提供し、より効果的なプラン作成をサポート。 |
| サービス担当者会議 | ・関係者が集まり支援内容を検討 ・ご利用者、ご家族の同意を得られればケアプランが確定 |
| サービス提供開始 | ケアプランに沿ってサービスが提供される |
| モニタリング | ・サービスの実施状況や目標の達成度を評価 ・必要に応じてケアプランの見直し |
| 給付管理 | ・利用実績に基づき、毎月10日までに国保連合会へ介護給付費・介護予防支援費・介護予防ケアマネジメント費を請求 |
全ての工程に社会福祉士が関わるわけではありませんが、多職種がそれぞれの専門性を活かしながら、チームとして包括的な支援を行っています。
社会福祉士が目指す地域包括支援センターのキャリアパス
地域包括支援センターでの業務は多岐にわたります。
そのため、日常の業務をこなしていくうちに、さまざまな人脈やスキルを身につけられます。
これらは、社会福祉士としての専門性を高め、多様なキャリアパスを開くための重要なステップとなるでしょう。
社会福祉士が地域包括支援センターで得られるスキル
地域包括支援センターで社会福祉士として働いていくと、以下のようなスキルを身につけられます。
- コミュニケーション力
高齢者やそのご家族、医療・介護関係者など、多様な立場の人々と円滑な意思疎通を図る能力が向上します - アセスメント力
表面的な問題だけでなく、潜在的なニーズやリスクを見抜き、多角的に状況を把握する力が養われます - 問題解決能力
複雑な課題に対し、関係機関と連携しながら、最適な解決策を見つけ出す力が身につきます - 制度に関する知識
介護保険だけでなく、医療保険や年金制度、生活保護など、幅広い制度に関する知識が深まります - 権利擁護スキル
虐待対応や成年後見制度の利用支援など、高齢者の権利を守るための専門知識と実践力が向上します - 多職種連携スキル
保健師や主任介護支援専門員など、他職種の専門性を理解し、チームとして協働する能力が高まります - 地域ネットワーク構築力
地域の関係機関やインフォーマルな資源を結びつけ、高齢者を支えるネットワークを構築する力が養われます
これらのスキルは、社会福祉士としての専門性を高めるだけでなく、将来のキャリアアップにもつながる貴重な財産となります。
経験を積んでステップアップする方法
地域包括支援センター経験を積むことで、センター長や基幹型地域包括支援センターの管理職としてのキャリアが視野に入ってきます。
また、具体的なキャリアとして、以下のようなステップアップが考えられます。
| 管理職 | ・センター長としてのキャリア ・基幹型地域包括支援センターの管理職 ・地域の福祉政策立案への参画 |
| 独立開業 | ・独立型社会福祉士としての開業 ・権利擁護の専門家として活動 ・成年後見人としての活動 |
| 専門性を活かした転職 | ・医療ソーシャルワーカー(MSW) ・社会福祉協議会での活躍 ・スクールソーシャルワーカー ・自治体のソーシャルワーカー |
キャリアアップを実現するためには、日々の実践に加えて、研修への参加や資格取得など、継続的な自己研鑽が重要です。
地域包括支援センターでの経験は、社会福祉士としての成長を促し、将来の可能性を広げてくれるでしょう。
なお、社会福祉士のキャリアアップに関する詳しい解説は、「社会福祉士はどのようにキャリアアップしていけばいい?(キャリア事例紹介)」をご参照ください。
地域包括支援センターの社会福祉士の給与・年収はどのくらい?
社会福祉振興・試験センターが2020年に実施した調査によると、社会福祉士全体の平均年収は403万円でした。
一方、地域包括支援センターで働く社会福祉士の平均年収は376万円という結果が出ています。
ただし、地域包括支援センターの給与はそれぞれの運営団体が定めるため、事業所や経験、雇用形態によって大きく異なります。
ご自身の経験や希望する働き方に合わせて、求人情報を詳しく確認することが重要です。
地域包括支援センターでの平均年収
地域包括支援センターにおける社会福祉士の平均年収について、以下の表をご覧ください。
| 雇用形態 | 平均年収 |
|---|---|
| 正規職員 | 392万円 |
| 派遣職員 | 370万円 |
| 契約社員 | 286万円 |
| パートタイム職員 | 188万円 |
出典:社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士就労状況調査(令和2年度)結果報告書(公益財団法人社会福祉振興・試験センター)
この表から分かるように、雇用形態によって平均年収には差があります。
しかし、地域包括支援センターでは、正規職員だけでなく、派遣職員や契約社員、パートタイム職員など、多様な働き方が可能です。
ご自身のライフスタイルやキャリアプランに合わせて、柔軟な働き方を選択できる点は、地域包括支援センターの魅力のひとつと言えるでしょう。
なお、社会福祉士の年収については『社会福祉士の年収はどのくらい?職場、職種、年齢別に徹底調査』を参考にしてください。
社会福祉士が地域包括支援センターで働くためのステップガイド
ここでは、地域包括支援センターで社会福祉士として働くための資格要件や採用プロセス、応募のポイントについて解説します。
地域包括支援センターで働くための資格要件
地域包括支援センターでは、社会福祉士・保健師・主任介護支援専門員の配置が義務付けられています。
社会福祉士として働きたいけど資格がないという場合でも、「社会福祉士に準ずる者」として認められれば、従事することが可能です。
「福祉事務所のケースワーカー経験5年以上」または「介護支援専門員経験3年以上」に加え、「高齢者相談援助業務経験3年以上」
出典:横浜市「地域包括支援センター職員の資格要件等について」
社会福祉士の配置基準は、各自治体の条例や方針により異なる場合があり、地域によって「社会福祉士に準ずる者」でも従事可能な場合と、社会福祉士の資格が必須とされる場合があります。
例として、東京都や大阪府では、社会福祉士の配置が強く推奨されているようです。
詳しくは、地域の福祉関連部署や各自治体のガイドラインを確認してください。
応募の際は、資格要件に加え、実務経験で基準をクリアしているかどうかも確認しましょう。
求人応募する際に確認しておきたいポイント
福祉人材は不足しているため、地域包括支援センターの求人も頻繁にあるケースが多いです。
運営法人によって福利厚生や勤務時間・定休日などの勤務条件が異なるため、募集要項をよく確認しましょう。
福祉の転職支援サービスである「「ケア人材バンク」の地域包括の社会福祉士求人」では、多数の求人から、こだわり条件を追加して意向に沿う求人情報を探せます。
また、地域包括支援センターの採用試験では、面接のほかに、小論文の作成や筆記試験が課される場合もあります。
これまでの実務経験や、地域福祉に対する意欲をアピールできるとよいでしょう。
まとめ
地域包括支援センターは、地域で暮らす高齢者を支えるための重要な機関です。
そのなかで社会福祉士は、相談援助や権利擁護、多職種連携などを通じて高齢者の生活を支えています。
「ケア人材バンク」では、地域包括支援センターの求人も多数取り扱っています。
希望どおりの転職を叶えるために、専任のキャリアパートナーによるサポートも実施しています。無料で利用できるので、まずは会員登録をしてみてください。