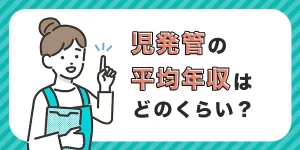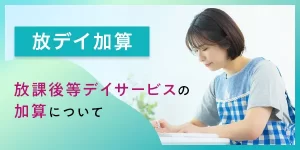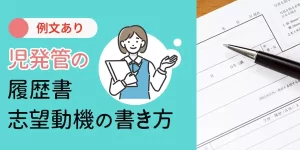児発管として個別支援計画を作成することになったものの、難しいし、これで合っているのか不安。様式を知り、もっとスムーズに作成ができるようになりたい。
初心者なら誰もが通る道かと思います。
この記事を読むことで、個別支援計画作成のポイントを抑えることができ、保護者が安心し、他の療育スタッフにもわかりやすい、個別支援計画の作成の参考にしていただければと思います。
目次
児童発達管理責任者(児発管)の役割と、個別支援計画の重要性
児発管の役割は以下の通りです。
- ご家族と目標の共有をすることで信頼関係構築に繋がり、支援内容の理解と協力が得られるようになる。
- 児発管による個別支援計画の作成は監査の対象となるため、適切な記録管理が求められる。
- 利用者様一人ひとりに行う具体的な支援の方向性を明確化することで、チーム全体が共通認識で一貫性のある療育の提供が可能になる。
個別支援計画の重要性として、以下の点が挙げられます。
- 利用者様の特性を記すことで、合理的配慮を施した環境設定を行いやすくなり、ご家族や利用者様が安心して施設を利用することができるようになる。
- 5領域※に沿った計画を立てることで、多面的な成長、将来的な自立、社会参加へと繋がる。
- 長期的な成長を見据え、スモールステップで取り組むべき支援計画を立てることで、無理のないペースで成長することができるようになる。
- 支援の実効性や成功が事業所の信頼性を左右する要となり、長期的な契約にも影響する。
※健康・生活、運動・感覚、認知・行動、言語・コミュニケーション、人間関係・社会性
児発管の個別支援計画の基本的な流れと作成手順
個別支援計画の重要性を理解したところで、ここからは作成手順を見ていきます。
ご家族にアセスメントを取る
まず初めにご家族や利用者様とアセスメント(ヒヤリング)を通して、情報収集を行います。
個別支援計画のためにアセスメントで確認する主な事項は以下の通りです。
- 生育歴や診断、手帳の有無など
- 現在の発達段階(できること、注意が必要なサポートについてなど)
- 発達特性(こだわりや感覚過敏などはあるか)
- 自傷行為や他害行為の有無と、普段の対応方法。
- アレルギーや服薬などの有無
- ご家族や利用者様自身の困りごと
- 利用者様の好きなこと・苦手なこと(遊びや興味関心)
- 受けたい療育
- できるようになってほしいこと
- デイでどのように過ごしてほしいか など
個別支援計画では5領域に沿った計画の作成が必要になるため、それらと照らし合わせて利用者様の発達段階や困りごとについて聞いておくと、作成がスムーズに行えるようになります。
作成時に困らないように、しっかりと情報を引き出し、ポイントを抑えておきましょう。
個別支援計画の原案を作成する
アセスメントを基に、個別支援計画の原案作成を行います。
項目は以下の通りです。
- 利用者及び、家族の生活に対する意向
- 総合的な支援の方針
- 長期目標
- 短期目標
- 5領域に沿った5つの支援目標
- 支援内容
- 達成期間
- 担当者、提供期間
- 留意点
- 優先順位
- 家族支援
- 移行支援
- 地域支援
- 作成日 など
原案には他スタッフにも確認をしてもらい、サインをもらう必要があります。
サービス担当者会議(カンファレンス)の実施と作成
原案を基に、他スタッフと『サービス担当者会議(カンファレンス)』を行い、情報の共有を行い、療育内容について他スタッフからも意見を募ります。
この会議を基に、原案の修正を行います。
個別支援計画の本案を作成する
サービス担当者会議で出た意見を原案に反映させ、ブラッシュアップした個別支援計画の作成を行い完成です。
ご家族に説明後、サインをもらう
完成した個別支援計画の内容をご家族に説明し、了承のサインをいただきます。
ここまでの一連の流れは、原則契約をした当月中に行いましょう。
内容に問題がなければ、作成した個別支援計画を基に療育をスタートします。
6ヶ月後にモニタリングを行う
個別支援計画は原則6ヶ月に一回、療育内容の見直しをする必要があります。
ご家族に施設に来所してもらい、利用者様の成長や最近の様子について情報交換を行います。
その中で達成した目標や、他に新たな困りごとがあれば、支援目標の変更を行います。
モニタリングで確認する項目は以下の通りです。
- 住所や連絡先、今後の利用頻度などに変更は無いか
- できるようになったことなど、成長の確認
- 利用者様の最近の家庭や学校などでの様子
- 最近の困りごと
- 前回の目標の達成度と継続の有無
- 達成した目標があれば、新たな目標の設定
- 長期目標・短期目標などの確認
原案作成からのサイクルを繰り返す
モニタリングを行い、発達状況を確認したら再度原案作成〜本案作成までのプロセスを6ヶ月周期で繰り返します。
利用者様の状態を把握しながら、PDCAサイクル(plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)で構成されるプロセス)を回すことで、利用者様にとって最善の支援を提供することができます。
児発管の個別支援計画を作成・活用するためのポイント
ご家族との連携と意見の尊重
作成した個別支援計画を活用するためには、ご家族との連携が不可欠です。
例えば、家ではご家族が利用者様の代わりにやっていることを、放デイでは療育として訓練をしても、利用者様は混乱し習得まで遠回りになったり、ストレスを与えかねません。
利用者様の将来を案じて療育を行いたいと思っても、現在ご家族がそれを望んでいないのであれば、意見を尊重し足並みを揃えた療育を行いましょう。
やり方を強要すると、利用回数の減少や最悪別の放デイへの移動にもなりかねません。
意見を尊重したうえで、
「こういうやり方もあって、他の子はそれで◯◯ができるようにになったケースもあります。」
と提案に留めるのが、長期的な目線では必要になってきます。
モニタリングと計画の見直し
モニタリングでは、ご家族と一緒に個別支援計画の見直しを行います。
最近のご家庭での様子をヒヤリングするほか、できるようになったことの確認などを行います。
また、6ヶ月間の療育の成果や放デイでの近況を報告し、利用者様が成長した点や継続して療育を行った方が良い点などをご家族に伝えます。
家、学校、放デイでは利用者様の見せている姿が違うこともよくあるので、ご家族からしっかりとヒヤリングを行い、情報交換を行うことが大切です。
支援内容だけでなく、ご家族の教育方針や考え方なども、このモニタリングでの会話を通して知ることができる貴重な機会です。
今後の療育や接し方に反映することで、信頼関係も築いていきましょう。
ヒヤリングを基に、優先した方が良い課題があった場合は、目標の入れ替えを行い、新たな目標設定を行います。
ご家族が目標の継続を希望した場合は無理に目標変更は行わず、目標はそのままに、成長に合わせた支援内容の見直しを行います。
支援計画の実施と評価
作成をした支援計画を基に、日々療育の実施を行います。
目標に応じて学習だけでなく、日々の生活に組み込んだり(例:片付け、挨拶など)、集団遊びなどを通して支援を行うこともあります。(例:協調性、ルールの遵守など)
支援を行う際は、利用者様の発達ペースに合わせながら興味関心に合わせるなどして、無理なく楽しみながら取り組めるような工夫をしましょう。
また、支援スタッフ全員が共通認識を持って支援にあたることが大切です。
日々の申し送りを通して支援の評価と、利用者様の発達段階の把握を正確に行うことができます。
そうすることで支援内容を次のステップに移行したり、あるいは難易度を下げるなど適宜評価と見直しを行いましょう。
フィードバックの反映
個別支援計画は作成して終わりではありません。
日々の申し送りなどによるフィードバックを個別支援計画に反映することで、より利用者様にとって最適な支援内容を提供することが可能になります。
- 文字を書く際に筆圧が弱く不安定
→段階を下げ、運筆や塗り絵などで筆圧向上と線の安定性を目的とした療育内容に修正 - 口頭での指示が入りにくい
→視覚支援のツール(絵カードなど)を活用して、視覚から入る情報を増やす。 - 宿題でつまずきが見られる
→学校やご家族に相談し、宿題の量や内容の見直しの依頼を行う。 など
フィードバックとなる情報をご家族、利用者様、スタッフから収集することで、多角的な目線で気付きを得ることができるようになります。
随時、療育内容の調整を行い、利用者様にとって最適な支援を提供していきましょう。
児発管の個別支援計画の記入例と様式
記入例① 就学に向けてできることを増やしたいAさんのケース
| 利用児および家族の 生活に対する意向 | 楽しく過ごしたい。(本人) 就学に向けて、切り替えやできることを増やしてほしい。(ご家族) |
| 総合的な支援の方針 | 就学に向けて学習支援や集団活動の経験を積み、できることを増やしていく。 |
| 長期目標 | できることを増やし、学校生活を楽しめるようになる。 |
| 短期目標 | 読み書きなどの理解を深め、自信を持てるようになる。 |
| 項目 | 支援 目標 | 項目 | 支援 内容 | 達成 期間 | 留意 事項 | 優先 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本人支援 | 箸で食事ができるようになる。 | 健康・生活 | 療育玩具を使って、お箸を使った遊びを活動に取り入れる。 | 6ヶ月 | 家庭と連携を取りながら行い、食事嫌いにならないように留意する。 | 4 |
| 本人支援 | 体幹運動を行い、姿勢の保持ができるようになる。 | 運動・感覚 | キッズヨガや動物競争などの体幹運動を取り入れ、体幹強化を目指す。 | 6ヶ月 | 学習時は発達に合った机・椅子の提供を行う。 | 5 |
| 本人支援 | ひらがなの読み書きに慣れる。 | 認知・行動 | 絵本や知育アプリを活用し、楽しみながら興味関心を深められるようになる。 | 6ヶ月 | 発達ペースに合わせ、興味関心を伸ばせるように支援を行う。 | 3 |
| 本人支援 | おもちゃの貸し借りが円滑にできるようになる。 | 言語・コミュニケーション | 適宜仲介に入り、気持ちの代弁などを行って適切な伝え方を教える。 | 6ヶ月 | 喧嘩や怪我などに繋がらないように留意する。 | 2 |
| 本人支援 | 集団行動に慣れることができるようになる。 | 人間関係・社会性 | 資格支援などを用いて見通しを立てやすくしたり、タイマーの活用などを行う。 | 6ヶ月 | 事前告知など行い見通しを立てることで不安を取り除けるように留意する。 | 1 |
| 家族支援 | 日々の生活の中で本人の意思を尊重しながら、様子の共有などを行う。 | ー | 連絡帳や申し送りを通して、日々の様子を都度お伝えし、共有する。 | ー | 保護者会の開催などを行い、グループワークや他の保護者とも繋がれる機会を設ける。 | ー |
| 移行支援 | 安心して就学ができるように情報の引き継ぎなどを行う。 | ー | 就学に合わせて情報の引き継ぎを行い、就学後の困りごとを最小限に抑えられるようにする。 | ー | 保護者の意向も確認しながら、三者で連携を図れるよう留意する。 | ー |
地域支援 | 関係機関で役割分担を行うと共に情報を共有し、支援等に役立つ具体策の提案を行う。 | ー | 連携会議を定期的に開催し、情報共有・役割分担について協議を行う。 | ー | 関係機関連携加算として、3ヶ月に一回程度の頻度での連携会議を開催予定。 | ー |
記入例② 特別支援学校に通うBさんのケース
| 利用児および家族の 生活に対する意向 | リラックスして過ごしたい。(本人) 友達と仲良く過ごしてほしい。(ご家族) |
| 総合的な支援の方針 | 本人なりのコミュニケーション力を伸ばし、友達を増やせるような機会を作る。 |
| 長期目標 | 自発的に友達に関わりに行くようになる。 |
| 短期目標 | おもちゃを介した集団遊びなどに参加できるようになる。 |
| 項目 | 支援 目標 | 項目 | 支援 内容 | 達成 期間 | 留意 事項 | 優先 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本人支援 | 90分定時排尿を促し、排泄の成功と拭き取りの経験を積む。 | 健康・生活 | 十分な水分補給の促しを行い、トイレでの排泄の成功に繋がるように支援する。紙の巻き取り練習などを行う。 | 6ヶ月 | トイレ介助は原則男性職員が行う。服の脱ぎ着や拭き取りの手本を見せ、わかりやすく伝える。 | 1 |
| 本人支援 | イヤマフやカームダウンスペースの使用を適宜促し、合理的配慮に務める。 | 運動・感覚 | 聴覚過敏の特性に配慮し、他の利用者が多い時や、気持ちが不安定な時は安心して過ごせることに務める。 | 6ヶ月 | 環境を事前に整え、他の利用者様には特性を説明し理解を促す。 | 2 |
| 本人支援 | おもちゃの貸し借りができるようになる。 | 認知・行動 | ロールプレイや絵本などを通して、他者との関わり方を学ぶ。 | 6ヶ月 | 他児とトラブルにならないように留意して見守る。 | 3 |
| 本人支援 | 要求や意思を言葉で伝える経験を増やし、伝える事の楽しさを知ってもらう。 | 言語・コミュニケーション | 絵カードマッチングや言葉図鑑などを通して、理解できる語彙を増やす。発語練習なども併せて行う。 | 6ヶ月 | 聞き取りにくくてもなるべく聞き返さず、失敗の経験を増やさないように留意する。 | 4 |
| 本人支援 | 同年代の他児に興味を持ち、ままごと遊びなどを一緒に行えるようになる。 | 人間関係・社会性 | 大人を含めた集団遊びの経験を増やし、他児と遊ぶことの楽しさを知れるように支援を行う。 | 6ヶ月 | 本人の興味のある遊びから始めることで、興味を持って参加できる工夫を行う。 | 5 |
| 家族支援 | 本人や家族の意思を尊重しながら、他児と関わる機会を増やしていく。 | ー | 連絡帳や申し送りを通して、日々の様子を都度お伝えし、共有する。 | ー | 保護者会の開催などを行い、グループワークや他の保護者とも繋がれる機会を設ける。 | ー |
| 移行支援 | 日常的な連携に加え、行事の時期などはより本人の気持ちに配慮した支援を行う。 | ー | 支援学校お迎え時などで申し送りを徹底し、ご家族にも情報の引き継ぎを行う。 | ー | 保護者の意向も確認しつつ、必要に応じて情報共有会議を開催する。 | ー |
地域支援 | 関係機関で役割分担を行うと共に情報を共有し、支援等に役立つ具体策の提案を行う。 | ー | 連携会議を定期的に開催し、情報共有・役割分担について協議を行う。 | ー | 関係機関連携加算として、3ヶ月に一回程度の頻度での連携会議を開催予定。 | ー |
まとめ
放デイでもリーダー的なポジションとなる児発管。
個別支援計画はポイントを押さえているかどうかで、他のスタッフの共通認識や療育のしやすさにも大きく影響する大切な業務です。
ポイントやコツを抑えることができれば、スムーズな作成が可能となりますのでぜひ何度でも読み返して手順や記入例を参考にしていただければと思います。
ケア人材バンクでは、他にも児発管向けの役立つ記事を多数掲載しているほか、児発管向けの転職支援サービスも行っています。
完全無料で転職サービスを受けることができますので、ぜひご登録のうえ転職エージェントにご相談ください。