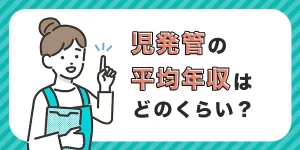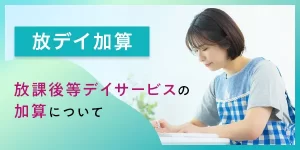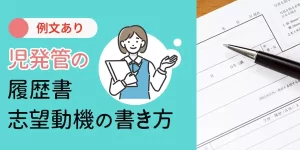児童発達支援管理責任者(児発管)業務で重要なのが個別支援計画書の作成です。
そのためには、丁寧なアセスメントが不可欠で、利用者様のニーズを適切に汲み取ることが大切です。
しっかりと寄り添うことで、より個々に合った計画書が作成できるようになります。
ここでは児発管におけるアセスメントの進め方、活用ポイントについて解説します。
目次
児童発達支援管理責任者のアセスメントの役割と重要性
アセスメントが持つ役割
児発管が行うアセスメントは、利用予定のお子様やご家族の困りごとを把握し、お子様の情報を収集することで、ニーズを正確に理解し、適切な療育につなげる重要な役割を担っています。
このアセスメントが適切に行われていないと、個別支援計画書の作成や療育の質にも影響を及ぼしてしまいます。
お子様の発達支援におけるアセスメントの重要性
アセスメントが適切に行われていないと、利用者様に関する情報が不足し、現場のスタッフがどのような療育を提供すべきか分からなくなってしまいます。
また、ニーズや発達状況、目標を正確に把握できていないと、保護者の方との意向と異なる療育につながる可能性があります。
そのため、現状を的確に把握し、ニーズをしっかりと分析した上で、ご家族と目標をすり合わせることが重要です。
これにより、分かりやすく実践しやすい個別支援計画書の作成が可能になります。
さらに、面談記録は実施指導の対象にもなるため、面談日・面談内容・記録者を明確に記録し、適切に管理しておきましょう。
アセスメントの進め方と個別支援計画の流れ
実際にどのようにアセスメントを実施するか、進め方の解説から、初回面談から評価までの一連のプロセスを見ていきましょう。
①.アセスメントの実施
利用前で一番最初に行うのが、アセスメントを取ることです。
通常、見学時や利用が決定した頃に行います。
アセスメントを通して、お子様の心身の状態や分析を丁寧に行い、目標やニーズの把握を行います。
アセスメント時に行う手順は以下の通りです。
- お子様本人とご家族の基本的な情報(住所、氏名、年齢、電話番号など)をアセスメントシートにご記入いただく
- 現在の発達状況(何がどのくらいできるか)について確認する
- 生育歴について確認する
- 困りごとやニーズについて聞き取りを行う
- 療育目標を大まかに決める
- 短期目標、長期目標、総合的な支援方針、お子様とご家族のニーズについて聞き取りを行う
必ずしもこの通りの流れで行う必要はなく、面談時の話の流れに合わせて臨機応変に聞き取りを行いましょう。
②.個別支援計画書の原案の作成
アセスメントを基に、個別支援計画書の原案を作成します。
アセスメント時に得た発達状況を反映させ、目標や環境設定などを記載します。
>>児童発達支援管理責任者の個別支援計画書作成についての記事はこちら
③.サービス担当者会議(カンファレンス)の開催
個別支援計画書の原案を基に、他スタッフとサービス担当者会議を行います。
現場のスタッフにアセスメントで得た情報を共有しつつ、支援目標の意見を募り、個別支援計画書の原案をブラッシュアップさせます。
④.個別支援計画の本案を作成する
サービス担当者会議で出た意見を基に原案を修正し、個別支援計画書の本案を作成します。
個別支援計画書が完成したら保護者の方に説明を行い、同意印をいただきましょう。
個別支援計画書に沿って、療育をスタートさせます。
⑤.モニタリングの実施
6ヶ月後に、お子様の発達面の再確認や目標の見直しのためにモニタリングを行います。
最初に取ったアセスメントも確認しながら、できるようになったことや興味の変化などを把握します。
⑥.1〜5のプロセスを繰り返す
6ヶ月周期でアセスメントを取り直し、個別支援計画書の原案作成からモニタリングまでの流れを繰り返します。
なお、アセスメントを取るタイミングは面談時だけでなく、進学など環境が変わるタイミングや、お子様に変化があったときにも行います。
アセスメントにおける保護者や関係者との連携方法
お子様の中には、進学や運動会などの行事による環境の変化、あるいは思春期に差し掛かる時期などに、気持ちが不安定になり、普段以上に手厚いサポートが必要になることがあります。
そのため、日頃から関係機関と連携を密にしておくことで、利用者様の困りごとにも迅速に対応しやすくなります。
- 学校、教育機関
- 保育園、幼稚園、療育園
- 他に通っている療育機関
- 相談支援事業所
- 医療機関 など
連携方法①.情報共有会議の開催
進学のタイミングや、癇癪(かんしゃく)が増えて不安定な時期などに、関係機関同士で情報共有会議を行うことは、普段とは異なる視点から利用者様の様子を知る貴重な機会となります。
この会議では、さまざまな意見を交換し、効果的な支援方法のヒントを得ることもできます。
また、お子様にとって、場所ごとに対応方法が異なることはストレスにつながる要因となります。
一貫した療育を目指すためにも、必要に応じて会議の開催を検討しましょう。
なお、保護者の方の同意を得た上でこうした会議を開催することで、関係機関連携加算の対象となります。
月に1回まで加算を受けることができるため、積極的に活用するのも良いでしょう。
連携方法②.関係機関への訪問
保育所等訪問という形で幼稚園・保育園、学校などと連携を取る方法もあります。
上記の保育所等に訪問を行い、事業所では見られにくい姿を確認したり、集団生活に適応できるように、それらの職員と連携を取りながら専門的な支援を行う福祉サービスです。
こちらも加算対象となっています。
児童発達支援管理責任者のアセスメントで把握すべきポイント
アセスメントを取る上で、最低限聞いておくと安心できる項目は以下の通りです。
主に聞いておくとよいのは、以下の5項目です。
- お子様ご本人の情報
- お子様を取り巻く環境の情報
- お子様の生育歴や、現在の発達状況
- ご家族の困りごと
- 総合的な支援方針とニーズ
これらの情報を聞き取りながら、後で読み返した際にわかりやすいように、発達の程度を数値化したり、◯や△などで評価しておくのもよいでしょう。
上記以外にも施設を利用するうえで確認しておきたいことがあれば、独自で追加して質問しても問題ありません。
お子様ご本人の情報
アセスメントを実施する際に必要なのは、発達面の情報だけではありません。
重大なトラブルを防ぐためにも、ご本人の基本的な情報をしっかりと把握することはとても重要です。
以下項目は最低限確認しておきましょう。
- 氏名、性別、住所、家族構成などの基本的な情報
- 連絡先
- 緊急連絡先
- かかりつけ医
- 既往歴
- 発達診断の有無
- 療育手帳や身体障がい者手帳の有無
- 投薬の有無
- アレルギーの有無
- 通っている園や学校
また、保護者の方が仕事をしている場合は、万が一に備えて、職場の連絡先も聞いておくことも大切です。
お子様を取り巻く環境の情報
園や学校、他の療育先での様子を把握することは、今後療育を進める上での大きなヒントとなります。
家庭と集団の中では見せている様子や困りごとも異なることが予想されるため、懇談での話や、各機関で立てている計画目標などを確認し、今後の支援の参考にしましょう。
- 習い事や他に通っている放課後等デイサービスなどについて
- 学校やクラスについてのほか、支援級などを利用しているか
- 進級や進学先の予定
施設によっては、利用日の振り替え案内をすることもあるかもしれません。
事前に習い事などによって利用が難しい日などを聞いておくと、今後のやり取りもスムーズです。
お子様の生育歴や現在の発達状況
アセスメントでは、お子様のこれまでの生育歴や、現在の発達段階を正確に把握することが、個別支援計画書を作るうえでとても重要になります。
チェックしておくと良い情報は以下の通りです。
- 生育歴について確認
- 身体的な発達や運動能力について
- 発語やコミュニケーション力はどの程度できるか
- 危機管理能力はあるか
- 身辺自立はどの程度できるか
- 読み書き計算への理解度や興味はあるか
- 自傷行為や他害行為の有無
- 感覚過敏などはあるか
- こだわりの行動などはあるか
- アレルギーや偏食、食事面での留意点
- 園や学校での様子について
- 家での様子について
- 興味のあること、好きなことについて
- 苦手なことについて
ご家族の困りごと
ご家族の方のお困りごとや悩みを把握することも大切です。
例えば以下のようなことから聞いてみると良いでしょう。
- 現在困っていることや不安なことは何か
- お子様にできるようになってほしいことは何か
- どのような療育が受けたいか
総合的な支援方針とニーズ
以下の目標・方針を踏まえたうえで、ご家族の方の希望している支援方針についてすり合わせを行いましょう。
- 長期目標
- 短期目標
- 総合的な支援方針 など
ご家族によっては、「できることを増やしてほしい」と願っている場合もあれば、「楽しく、友達と仲良く過ごしてほしい。療育はできる範囲でお願いしたい。」というケースもあります。
このようにご家庭によって子育て方針やニーズは異なるため、聞き取りを行いながら支援の方向性を確認しましょう。
また、発達面のことだけではなく、送迎の希望や仕事の都合による利用時間の希望についても確認をしておくとよいでしょう。
効果的なアセスメントを行うための実践的な方法
ここではより効果的なアセスメントを行うために、特に意識したいポイントをまとめました。
提供できる療育内容を具体的に伝える
職員のスキルや揃えている療育道具などで、提供できる療育は施設によって多少異なります。
勤めている施設で強みにしていることや、実施している療育を具体的に伝えることで、アセスメント中にご家族の方から、
「そういうこともやってもらえるんですね!」
「確かに困っていました。」
などといった反応も得られ、ニーズを引き出すきっかけにもなります。
また、提供できる支援を明確にしておくことで、ご家族の方と施設双方が不安なく支援につなげることができるようになります。
アセスメントツールやチェックリストの活用
アセスメントを行う前に、アセスメントシートやチェックリストを準備しておくことをおすすめします。
これらを活用することで、スムーズに情報を引き出せるだけでなく、確認すべき項目を漏れなく把握することができます。
アセスメントシートは、一部のWebサイトからダウンロードできるほか、事業所ごとに独自のシートを用意している場合もあります。
また、モニタリングの前にアセスメントシートを見直すことで、利用者様の成長した部分を具体的に把握しやすくなります。
5領域に沿ったアセスメントを実施
アセスメントを行う目的は、利用者様の発達状況を正確に把握したのち、それに基づいて個別支援計画書を作成し、適切な療育を提供するためです。
個別支援計画書は「5領域(【健康・生活】、【人間関係・社会性】、【運動・感覚】、【認知・行動】、【言語・コミュニケーション】)」に沿って計画を立てる必要があるため、アセスメントの時点で各領域ごとの発達状況の確認と、おおまかな目標設定も行いましょう。
ただし5領域について馴染がないご家族もいるため、各領域に合わせた具体的な療育などもまとめておくと、伝わりやすくスムーズに目標設定がしやすくなります。
また、利用者様が苦手としている分野に偏らず、総合的に情報が得られるというメリットもあります。
まとめ
児発管が担う大切な業務の1つ「アセスメント」を適切に行い、必要な情報を得ることは、後に作成する個別支援計画書において非常に重要です。
また関係機関とも適宜連携を取りながら進めることで、お子様にとってよりインクルーシブな療育や適切な見守りに繋げることができます。
ケア人材バンクでは、他にも児発管向けの役立つ記事を多数掲載しているほか、児発管向けの転職支援サービスも行っています。
完全無料で転職サービスを受けることができますので、ぜひご登録のうえ転職エージェントにご相談ください。