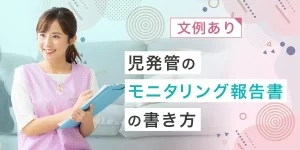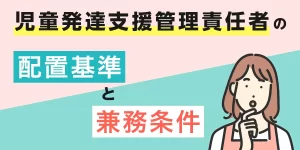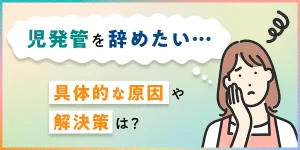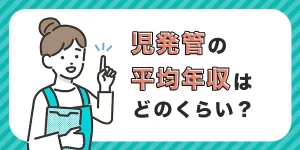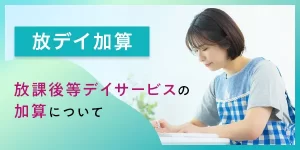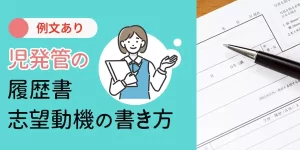この記事では、放課後等デイサービス(放デイ)の仕事内容について詳しく説明しています。
「どんな仕事をするの?」「働くのに資格は必要?」といった疑問はありませんか?この記事を読めば、一日の仕事の流れから必要な資格、仕事のやりがいまで、放デイで働くイメージが具体的につかめます。
仕事への理解を深め、自分に合った職場探しの第一歩にしてください。
目次
放課後等デイサービス(放デイ)って、どんなところ?
障がいをお持ちのお子様や、発達に特性のあるお子様たちが、放課後や夏休みなどの長期休暇中に専門的な支援(療育)を受けたり、安心して過ごしたりできる「福祉サービス」です。
「学童保育」と混同されることもありますが、放課後等デイサービスは単に子どもを預かるだけでなく、一人ひとりの成長や自立をサポートするという明確な目的を持っています。
具体的にどのような場所なのか、3つのポイントで見ていきましょう。
利用できるのは「6歳~18歳の支援が必要なお子様」
対象となるのは、小学生から高校生まで(6歳~18歳)の就学児です。
利用するには、お住まいの市区町村の役所で申請し、「通所受給者証」の交付を受ける必要があります。
主な役割は「専門的な療育」と「安心できる居場所づくり」
放課後等デイサービスは、子どもたちが将来社会で自立していくためのスキルを育む「療育」の場です。
同時に、学校や家庭とは違う第三の「安心できる居場所」としての役割も担っています。 事業所では、以下のような支援を組み合わせて提供しています。
- 自立支援:着替えや片付けなど、日常生活に必要なスキルを身につける練習
- 社会性の向上:集団活動や遊びを通して、コミュニケーションスキルやルールを学ぶ
- 学習支援:宿題のサポートや、個々の課題に合わせた学習
- 創作・運動・音楽活動:様々な体験を通して、成功体験を積み、興味関心を広げる
この他にも、公園へのお出かけや買い物体験、クッキングなど、社会との繋がりを意識した活動を行う事業所も多くあります。
事業所によって特色が違うため、お子様に合う場所選びが重要
放課後等デイサービスは、事業所ごとに療育方針やプログラム、対象としている子どもの特性などが大きく異なります。
運動療育に力を入れているところ、学習支援が手厚いところ、芸術活動が豊富なところなど、様々です。
そのため、利用を検討する際は、必ず見学に行き、お子さんの特性やご家庭の希望に合った事業所を選ぶことが非常に大切です。
放課後等デイサービスの仕事って、具体的に何をするの?
子ども一人ひとりに合わせた療育や自立支援が中心です。
その他、学習サポートや送迎、保護者との連携など、業務は多岐にわたります。
放課後等デイサービスは、単に子どもを預かるだけの場所ではありません。子どもたちが将来、社会で自立して生活していくためのスキルを育むことを目的としており、そのための専門的な支援が仕事の中心となります。
具体的な業務内容は以下の通りです。
- 個別・集団での療育:個別支援計画に基づき、子どもの発達段階や特性に合わせた支援や、集団活動を通して社会性を育むトレーニングを行います。
- 創作活動・レクリエーション:季節のイベントや創作活動、運動などを通して、子どもの興味関心を広げ、成功体験を積めるような機会を提供します。
- 学習支援:学校の宿題のサポートや、個々の課題に合わせた学習支援を行います。
- 基本的な生活習慣の指導:手洗いや片付けなど、日常生活に必要なスキルが身につくようサポートします。
- 送迎業務:学校や自宅への送迎を行います。
- 保護者との連携:面談や連絡帳などを通して、子どもの様子を共有し、家庭と連携して支援を進めます。
- 事務作業:支援記録や個別支援計画書の作成などを行います。
放課後等デイサービスの職種って、それぞれどんな仕事をするの?
施設の運営や計画作成を担う「児童発達支援管理責任者」、子どもと直接関わる「児童指導員・保育士」が中心となる職種です。
さらに、療育の専門性を高める様々な専門職がチームで連携し、子どもたちを支えています。
ここでは、放課後等デイサービスで活躍する主な3つの職種と、チーム支援を充実させる専門職について、具体的な仕事内容や一日の流れをご紹介します。
施設の司令塔!計画作成と管理を担う「児童発達支援管理責任者(児発管)」
「児発管(じはつかん)」とも呼ばれる、各事業所に配置が義務付けられている施設の責任者です。
保護者との面談を通して個別支援計画を作成し、療育が計画通りに進んでいるかを管理するほか、現場スタッフへの指導・管理も行うなど、施設の司令塔として重要な役割を担います。
| 時間 | 活動内容 |
|---|---|
| 9:00 | 出勤・環境整備・メールチェック・情報共有 |
| 9:30 | 事務作業・記録整理 |
| 10:30 | 関係機関との連絡調整・会議準備 |
| 11:30 | 個別支援計画作成・モニタリング準備 |
| 12:30 | 昼休憩 |
| 13:30 | スタッフミーティング・支援内容確認 |
| 14:00 | 児童の受け入れ準備・保護者対応(必要に応じて) |
| 14:30 | 児童の様子の観察・個別対応・指導員への助言 |
| 16:00 | 保護者面談・相談対応(予約に応じて) |
| 17:00 | 児童の降所対応・保護者への情報共有 |
| 17:30 | 記録入力・スタッフとの振り返り・翌日準備 |
| 18:00 | 退勤 |
支援の主役!子どもに寄り添い療育を行う「児童指導員」
子どもたちと直接関わる時間が最も長い、現場の中心的な存在です。個別支援計画に基づき、日々の遊びや集団活動を通して療育を行うほか、子どもたちの送迎、おやつの準備、施設の清掃など、安全で楽しい環境づくり全般を担います。
| 時間 | 活動内容 |
|---|---|
| 10:00 | 出勤・環境整備・活動準備 |
| 11:00 | 事務作業・記録(前日分など)・教材作成 |
| 12:00 | 昼休憩 |
| 13:00 | スタッフミーティング・送迎ルート確認 |
| 13:30 | 送迎業務(学校へお迎えなど) |
| 14:30 | 児童の受け入れ・健康チェック・荷物整理サポート |
| 15:00 | 宿題サポート・自由遊びの見守り |
| 15:45 | おやつの提供・準備・片付けサポート |
| 16:15 | 集団活動・療育プログラムの実施 |
| 17:15 | 降所準備・帰りの支度サポート・清掃 |
| 17:30 | 送迎業務(自宅へお送りなど)・保護者への簡単な報告 |
| 18:00 | 記録作成・翌日準備・戸締り |
| 18:30 | 退勤 |
保育の専門性を発揮!現場を支える「保育士」
基本的な仕事内容は児童指導員と同様ですが、保育士としての専門性が特に活かせる職種です。
発達に関する知識に基づいた関わりや、絵本の読み聞かせ、手遊び、ペープサートといった保育のスキルを活動の企画・提案に反映させることで、療育の幅を広げることが期待されます。
| 時間 | 活動内容 |
|---|---|
| 10:00 | 出勤・施設内環境設定・遊具点検 |
| 11:00 | 個別支援計画の確認・活動準備(製作物の準備など) |
| 12:00 | 昼休憩 |
| 13:00 | スタッフミーティング・情報共有 |
| 13:30 | 送迎業務(学校へお迎えなど) |
| 14:30 | 児童の受け入れ・バイタルチェック・情緒の安定を図る声かけ |
| 15:00 | 宿題の見守り・個別課題への取り組みサポート |
| 15:45 | おやつの時間・食育の要素を取り入れた関わり |
| 16:15 | 主活動(設定保育)・遊びを通じた発達支援 |
| 17:15 | クールダウン・帰りの準備・絵本の読み聞かせなど |
| 17:30 | 送迎業務(自宅へお送りなど)・保護者への丁寧なフィードバック |
| 18:00 | 保育記録の作成・保育環境の整備・翌日の活動準備 |
| 18:30 | 退勤 |
その他、チーム支援を充実させる様々な専門職
上記の職種に加え、以下のような専門スタッフが連携することで、より手厚く、多角的な支援が実現します。
- 管理者:事業所全体の運営・管理、スタッフの労務管理、行政機関との連携などを担う事業所のトップです(児発管が兼任する場合も多い)。
- 理学療法士(PT):「歩く」「立つ」など、身体の基本的な運動機能の向上をサポートします。
- 作業療法士(OT):遊びや作業を通して、着替えや食事といった日常生活動作や、手先の器用さを育みます。
- 言語聴覚士(ST):「話す」「聞く」といったコミュニケーションや、食事の飲み込み(摂食嚥下)を支援します。
- 心理指導担当職員:公認心理師・臨床心理士などが、子どもの心理状態をアセスメントし、専門的な観点から心のケアを行います。
- 嘱託医:医療的ケアが必要な子どもがいる施設において、診察や治療などを行います(非常勤での関わりが多い)。
児発管の転職相談受付中
児発管転職サポートに登録(完全無料)放課後等デイサービスで働くのに、どんな資格が役立ちますか?
「児童指導員」として働くための任用資格(保育士、教員免許など)が基本です。
さらに、福祉・医療・リハビリ・心理系の専門資格があれば、より質の高い療育に貢献でき、キャリアアップにも繋がります。
放課後等デイサービスでは、様々な専門性を持った職員がチームで働いています。
ここでは、特に役立つ資格を役割ごとに分けてご紹介します。
事業所の要!個別支援計画を作成する「児童発達支援管理責任者」
個別支援計画の作成・管理を担う、各事業所に配置が義務付けられている専門職です。
実務経験と研修を修了することで就くことができ、キャリアアップの大きな目標となる資格です。 (※必要な実務経験年数はお持ちの資格により異なります。)
福祉の専門知識で支援の質を高める資格
福祉の専門家として、子どもや保護者への相談援助業務でその知識を大いに活かせます。
- 社会福祉士
福祉全般の幅広い知識を活かし、関係機関との連携やソーシャルワークを担います。 - 精神保健福祉士
心のケアの専門家として、二次障害の予防など、子どもと保護者の精神的なサポートを行います。
お子様と関わる経験を直接活かせる資格(児童指導員の要件)
これらの資格を持つ方は「児童指導員」として働くことができます。
教育・保育現場での経験は、療育の場面で即戦力となります。
- 保育士:発達に関する専門知識や、手遊び・歌などの豊富なレパートリーが大きな強みになります。
- 教員免許・幼稚園教諭:教育的な視点を活かした学習支援や、集団活動の運営で力を発揮できます。ピアノなどのスキルも役立ちます。
医療・リハビリの専門性で療育の幅を広げる資格
リハビリの国家資格を持つ専門職(機能訓練担当職員)がいることで、より専門的な療育を提供できます。
- 理学療法士(PT)
身体の基本的な動きにアプローチし、遊びを通して運動機能の向上を促します。 - 作業療法士(OT)
食事や着替えなど、日常生活の応用的な動作がスムーズにできるよう支援します。 - 言語聴覚士(ST)
言葉の発達やコミュニケーションに課題のある子どものサポートを行います。 - 看護師
医療的ケアが必要な子どもがいる施設では必須の存在。日々の健康管理や急な体調変化への対応でも頼りになります。
心の専門家として子どもと保護者に寄り添う資格
心理的なアプローチから、子どもと保護者の双方をサポートします。
- 公認心理師・臨床心理士
子どもの心理状態をアセスメント(評価)し、適切な関わり方を提案します。保護者のカウンセリングを担うこともあります。
放課後等デイサービスで働く魅力って、具体的に何ですか?
お子様の成長を間近で支えられるやりがいはもちろん、専門的な支援スキルが向上し、安定した需要の中で地域社会に貢献できるのが大きな魅力です。
放課後等デイサービスの仕事には、大変な面もありますが、それを上回る多くのやりがいやメリットがあります。
具体的に、どのような魅力があるのかを3つのポイントに分けて解説します。
保護者や地域と連携し、社会に貢献できるやりがい
私たちの仕事は、施設内で子どもと関わるだけではありません。日々のコミュニケーションや相談対応を通じて、子育ての悩みや不安を分かち合うことで保護者を支える重要な役割を担います。
また、学校や行政、地域の関連施設と連携し、地域全体で子どもを育むネットワークの一員としても活動します。
こうした人との繋がりの中で、地域の子育てや福祉を直接支えているという実感を得られるのは、この仕事ならではの大きなやりがいです。
子ども一人ひとりと向き合い、専門スキルが向上する
放課後等デイサービスには、発達障がい(ADHD・ASD・LDなど)や知的障がいなど、様々な特性を持つ子どもたちが通っています。
マニュアル通りの対応ではなく、一人ひとりの個性や発達段階を深く理解し、その子に合った支援を考え、実践していくことが求められます。
「子どものために何ができるか」を常に考え、試行錯誤するプロセスそのものが、他では得られない貴重な知識と経験になり、自身の専門性を着実に高めることに直結します。
社会的な需要が高く、将来性があり長く続けられる
近年、支援を必要とする子どもたちの増加に伴い、放課後等デイサービスの事業所数は全国的に増え続けており、その需要は今後も高まっていくと予測されています。
社会に不可欠なサービスであるため、景気に左右されにくく、安定して働き続けることが可能です。
さらに、働きながら資格を取得したり、経験を積んだりすることで、児童発達支援管理責任者(児発管)などの管理職を目指すこともできます。
将来を見据えて、長く活かせる専門的な経験を積みたい方にとって、非常に魅力的な職場環境です。
放課後等デイサービスの仕事って、やっぱり大変ですか?
仕事量の多さや専門的な対応の難しさなど、大変な面はあります。
しかし、適切に対処することで、チームでの協力や経験を積むことで乗り越えていくことで、チームワークやお子様をより深く理解できるチャンスにもなります。
どのような仕事にも厳しさはありますが、事前に内容と対処法を知っておくことで、心構えができます。
実際に働く方から聞く「大変な点」と、その乗り越え方を3つのポイントに分けて解説します。
業務範囲が広く仕事量は多いが、チーム連携で乗り越える
療育の提供はもちろん、日々の支援計画の作成や活動の準備、学校や自宅への送迎など、放課後等デイサービスの業務は多岐にわたります。利用するお子様の人数が多ければ、その分、個別に対応すべきことも増えるため、一人で全てを抱えるのは困難です。
だからこそ、スタッフ同士で日頃から密にコミュニケーションを取り、適切に役割分担することが不可欠です。
お互いに気遣い、協力し合える良い関係性を築くことが、質の高い支援と自身の負担軽減に繋がります。
専門的な対応に悩み、経験不足を感じることがある
様々な特性を持つお子様と関わる中で、知識や経験が足りず、対応に困ってしまう場面は誰にでも起こり得ます。特に新人時代は、自分の無力さを感じてしまうかもしれません。
大切なのは、一人で抱え込まないことです。
入所時のアセスメント(情報収集・評価)をチームでしっかり共有し、対応方法を相談しましょう。
すぐに完璧にできなくても、経験豊富な先輩の動きから学び、誠実にお子様と向き合うことで、少しずつ特性への理解が深まり、自信を持って対応できるようになります。
事業所ごとに方針が異なり、ミスマッチが起こりうる
一口に放課後等デイサービスと言っても、その支援方針は様々です。運動療育に力を入れている施設、音楽療法や学習支援を主軸にしている施設など、特色は大きく異なります。また、受け入れるお子様の障害の重さや年齢層を限定している場合もあります。
この「違い」は、自分に合わない職場を選んでしまうと「大変さ」に繋がります。
転職や就職活動の際は、必ず事前に事業所の見学に行きましょう。
実際に支援の様子を見たり、職員の方に話を聞いたりして、施設の雰囲気や価値観が自分に合っているかを確かめることが、ミスマッチを防ぐ最も有効な方法です。
放課後等デイサービスと児童発達支援の違いは?
放課後等デイサービスと児童発達支援は、どちらも児童福祉法に基づく発達支援サービスですが、対象となる子どもの年齢が異なるため、支援の重点や働き方に違いがあります。
具体的に以下のような違いがあります。
| 比較項目 | 放課後等デイサービス | 児童発達支援 |
|---|---|---|
| 対象年齢 | 原則として6歳~18歳の就学児(小学生・中学生・高校生) | 原則として0歳~6歳の未就学児 |
| 主な目的・関わり方 | 学校生活への適応や、将来の自立を見据えた社会的スキル・生活スキルのトレーニング | 日常生活における基本的な動作の習得や、集団生活への準備など、発達の土台作り |
| 主な利用時間帯 | 放課後~18時頃まで(夏休みなどの長期休暇中は日中から利用) | 日中~16時頃まで |
| 根拠法 | 児童福祉法 | 児童福祉法 |
放課後等デイサービスと学童保育の違いは?
最も大きな違いは「目的」です。
放課後等デイサービスは「療育」が目的の福祉サービス、学童保育は「安全な生活の場の提供」が目的の子育て支援事業です。
放課後等デイサービスと学童保育(放課後児童クラブ)は、利用を検討する際に混同されやすいサービスですが、目的や対象などに下記のような違いがあります。
| 比較項目 | 放課後等デイサービス | 学童保育 (放課後児童クラブ) |
|---|---|---|
| 根拠法 | 児童福祉法 | 児童福祉法 |
| 管轄 | 厚生労働省 | こども家庭庁 |
| 目的 | 障害のある子どもの自立支援・療育、居場所の提供 | 保護者の就労支援、子どもの健全な育成と安全確保 |
| 対象 児童 | 支援の必要な6歳〜18歳の就学児(小・中・高校生) | 保護者が就労等で昼間家庭にいない主に小学生 |
| 人員 配置 | 児童指導員、保育士、理学療法士などの専門職の配置が義務付けられている | 放課後児童支援員などの配置が義務付けられている |
| 利用 方法 | 市区町村で通所受給者証の交付を受ける必要がある | 市区町村や運営する民間事業者への申し込みが必要 |
放課後等デイサービスの仕事に向いているのはどんな人?
放課後等デイサービスの仕事には、以下のような特徴を持つ人が向いています。
- 子どもが好きで、成長を長期的に見守れる人
- 一人ひとりの特性に合わせた支援ができる、根気強さと忍耐力がある人
- 保護者や関係機関と円滑に連携できるコミュニケーション能力が高い人
- 子どもの些細な変化や成長に気づける観察力がある人
- チームで協力して仕事を進めるのが得意な人
- 課題解決に向けて、柔軟な発想で工夫できる人
まとめ
放課後等デイサービスの仕事内容について解説しました。
仕事は多岐にわたりますが、一緒に働くスタッフと協力し、支援していく楽しさがあります。
放課後等デイサービスで働くイメージを持ち、一歩踏み出してみてはいかがですか?
「ケア人材バンク」では、障がい福祉資格向けの転職支援サービスを行っています。
完全無料の転職支援サービスですので、気軽にご相談ください。
ご登録お待ちしております。
✨ 気になったらSNSシェア ✨
※当サイトの情報は、掲載時点での情報に基づいています。また、情報の正確性、最新性を保証するものではありません。