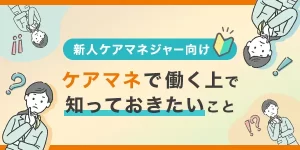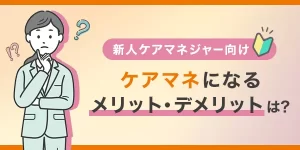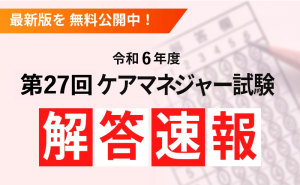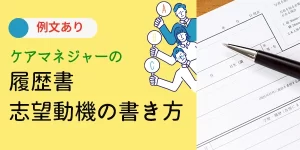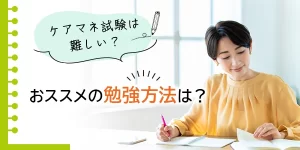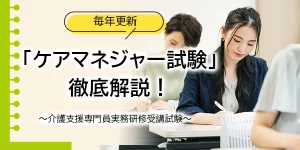居宅ケアマネと施設ケアマネとでは仕事内容や役割、働き方や求められるスキルまで違いがあります。
「居宅ケアマネが合っているかや施設ケアマネが合っているか」
「居宅ケアマネと施設ケアマネではどちらが大変か」
などは、実際に働く職場によって大きく変わっていきますが、ここでは、一般的な居宅ケアマネと施設ケアマネの働き方を比較をしながら、どのような違いがあるのかを解説していきます。
それぞれの特徴を知ることで、自分に合った働き方はどちらなのかが分かるようになるでしょう。
目次
居宅ケアマネと施設ケアマネの役割の違い
居宅ケアマネと施設ケアマネでは、求められる役割が違います。
居宅ケアマネの場合は、行政や他事業所などの外部とチームになって働くことが多いですが、施設ケアマネの場合は、施設内の介護士・看護師・相談員など内部とチームになって動いていきます。
では、それぞれで一体どのような役割が求められるのか見ていきましょう。
居宅ケアマネの役割
外部事業所との連携の円滑化
在宅で介護保険を利用する場合、様々な事業所と連携を図りながら利用者様の支援を行うため、居宅ケアマネは外部事業所との連携を円滑にしていく必要があります。
ケアマネが連携しづらい事業所であっても、利用者様のご希望やニーズに合っている事業所であれば、連携していかなければいけないため、精神的にしんどくなることもあるかもしれません。
しかし、外部事業所と連携するというのは、様々な支援者と顔見知りになり、ネットワークを広げていくことができるので、居宅ケアマネのおもしろいところでもあります。
単位数の管理
居宅ケアマネは、サービスごとの単位数をきっちりと管理し、利用者様が支給限度額を超えないようにしなければなりません。
支給限度額は、要介護認定区分ごとに設定されています。
支給限度額内であれば介護保険の適応になりますが、万が一支給限度額を超えてしまうと、超えてしまった分は保険適応にならず、利用者様が10割支払わないといけなくなってしまいます。
そのため単位数管理は、居宅ケアマネにとって重要な仕事の一つです。
ケアマネが加算をつけるのを忘れていたために、あとで支給限度額を超えていることが分かった、支給限度額を超えることが事前に分かっていたにもかかわらず、事前に利用者様、ご家族へ説明しておらず、説明責任を果たせていなかったため利用者様に謝罪したという経験をしている居宅ケアマネもいると聞きます。
利用者様に寄り添う
施設サービスはある程度、業務マニュアルが決まっている中での支援になりますが、在宅サービスは、形の決まっていない中で、利用者様の望む生活を実現するためのケアプランを作成していかなければなりません。
- 家で入るか、施設(通所サービス)で入るか
- 家で入る場合でも、ヘルパーにお願いするのか、看護師にお願いするのか等、
一つのニーズでも、利用者様ごとにどのサービスが適切か、どの事業所が合っているのか等、数ある選択肢の中から利用者様に寄り添い、どれがよいのか一緒に考え支援していく必要があります。
これだけ聞くと居宅ケアマネは大変なように聞こえるかもしれませんが、利用者様の望む生活に向けて一緒に支援していけるので、とてもやりがいのある仕事です。
施設ケアマネの役割
施設内での連携の円滑化
施設ケアマネは、主に施設内の他職種との連携を行っていきます。
特に、日頃直接ケアに関わっている介護士・看護師とは密な連携が必要です。
この際、ケアマネに求められることは施設内での連携をスムーズに行うことです。
ケアマネが他職種、他部署との関係が良くなかった場合は、ケアプランのモニタリングや、カンファレンス、評価、目標設定など利用者様が必要とするケアプランにすることが難しくなります。
また、施設内の利用者様はコミュニケーションを取ることができない方も多いです。
その場合は、一番身近で日頃からケアしている職員とは密な連携を図る必要があります。
普段から、コミュニケーションを図りつつ、分からないことは「聞く」という姿勢を持ち、感謝を忘れないようにしましょう。
施設内の人間関係の構築は何より重要で、ここが上手く行けば結果的に良いケアプランとなり、利用者様にもご家族にも喜ばれることでしょう。
介護度や介護保険の更新時期の把握
施設で暮らしていると、ご家族は介護度や介護保険の更新時期を知らない方が多いです。
その際には、ケアマネが介護度の把握を行い、必要に応じて介護度の区分変更申請を代行する必要があります。
病気や転倒事故などで急に介護度が重くなる場合があり、その際には、ご家族に説明をして、介護度の区分変更をする必要があります。
介護保険の更新時期を毎月確認し、申請をすることで更新を忘れて自己負担になってしまうことを避けることができます。
また、施設によっては、介護保険の認定調査員の資格を取ってほしいと言われる場合があります。
施設内の利用者様が介護保険の更新の場合、施設ケアマネがその利用者様の認定調査ができる場合もあります。
その場合、自分がよく知っている状態や介護士や看護師に確認をしながらできるので、より正確な調査が可能になります。
利用者様やご家族との信頼関係の構築
施設でのケアマネの場合、ご家族と顔を合わせる機会が少なくなります。
そのため、面会に来た際には、ケアマネということを説明した上で、ご家族の悩みや表情、希望することなどをしっかりと聞き取る必要があります。
また、よく面会に来てくださるご家族とは毎回しっかりと挨拶をして、関係を築いていく必要があります。
時折、ケアをしている職員とご家族との思いや意見の食い違いが見られる場合があります。
その際は、カンファレンスを開催し、お互いの意見や、どのようにしたら利用者様により良いサービスが提供できるかを一緒に考えていく必要があります。
カンファレンスで、この人なら安心して意見が言えると思えるような関係が築けるように、利用者様とご家族とは、積極的にコミュニケーションを図っていきましょう。
居宅ケアマネと施設ケアマネの役割を比較
居宅ケアマネと施設ケアマネの役割を表で見てみましょう。
| 居宅ケアマネ | 施設ケアマネ | |
|---|---|---|
| 外部(行政・病院・他事業所)との連携 | 外部との連携によってケアプランが成立するため必ず必要 | 必要な場合はあるが、限られており、居宅ケアマネに比べたら少ない |
| 内部(職場内)の連携 | 信頼関係や助け合える関係は必要であるが、密な連携は不要 | 職場内でのモニタリング、カンファレンス、評価などを行うため、普段接している担当職員との連携は必ず必要 |
| 利用者様やご家族との信頼関係 | 利用者様とご家族に納得して、サービスを利用していただけるような配慮が大切 | ご家族と会う機会が少ないこともあり、ご家族に施設での状況を的確に伝えることが大切 |
| 介護保険の更新時期の把握 | 介護保険の更新を忘れていると、利用しているサービスが全額自己負担となってしまう。 ケアマネが代理で申請が可能なため、代理申請をすることも多い | |
| 単位数の管理 | 担当利用者様の単位数は、しっかりと把握し、利用者様やご家族に伝える | 1ヶ月単位で決められた料金を払うことが多いので、単位数の把握は求められないことが多い |
居宅ケアマネと施設ケアマネの働き方の違い
居宅ケアマネと施設ケアマネの役割の働き方は大きく違いがあります。
その1つにあげられることが、勤務時間です。
居宅ケアマネは、日中の活動がメインですが、施設ケアマネの場合、介護士などと兼務していると夜勤なども含まれてきます。
「思っていた働き方と違うな」と就職して困らないように、それぞれの違いをしっかりと把握しましょう。
居宅ケアマネの働き方
日勤帯のみの勤務
居宅ケアマネは基本的に平日日勤帯の勤務です。
施設併設の居宅ケアマネの場合は、宿直があったり、オンコール体制を取っている事業所は、休みの日に携帯電話を持ち帰らないといけない事業所もあります。
また、ここ最近はご家族もお仕事をされているケースが増えており、ご家族の都合に合わせ、土曜日に出勤したり、時間外に訪問したり、電話をしないといけないケースも時々あります。
育児や介護中で、残業や土曜日出勤ができない場合は、事前にその旨を職場へ伝え、時間外対応しないといけなくなるケースは担当から外してもらうようにしましょう。
テレワーク等を導入する事業所も増加
居宅ケアマネの場合、福祉業界では、なかなか実現できなかった在宅ワーク、フレックス制度を取り入れ、自由な働き方ができる事業所が増えてきています。
会社から支給されたパソコンを使い、家で仕事をしてもよい、事業所に来て仕事をしてもよい、出社時間は自由、という働き方ができるところも増えてきていると聞きます。
育児や介護中で、しばらく家で仕事をしたい、昨日は飲み会で帰りが遅かったから今日は遅めに出勤したい、病院へ行きたいから今日は早めに帰りたい、という日があるかと思います。
そのような場合、今までは福祉業界で働くことを諦めていた方でも、事業所を選べば、仕事を継続することができます。
また、経験を積み、ひとりケアマネとして働くのであれば、誰に管理されるわけでもなくより自由な働き方ができるという選択もあります。
1ヶ月の業務内容はほぼ同じ
居宅のケアマネ業務は、1ヶ月単位でほぼ変わりません。
以下のようなルーティンが一般的です。
- 初月に前月利用分の実績を入力
- 1ヶ月の間にモニタリングや新規利用者様の契約、サービス担当者会議などを行う
- 月末に提供票を作成する
慣れてきたら、前倒しで業務をこなしていけるようになります。
もちろん、急な対応、予定になかったサービス担当者会議を開催しなければいけない等はありますが、基本的にやることは同じなので、経験を積むことで効率よく仕事をこなしていくことができます。
また、居宅ケアマネは、担当できるケースの上限が決まっているため、上限までケースを担当すれば、新たなケースを担当しなくてもよいので予定を立てやすいです。
施設ケアマネの働き方
施設の利用者様のケアプラン作成
施設で生活されている方のケアプランを作成します。
施設ケアマネは、担当件数が最大100人までの利用者様を持つことができるため、1人でたくさんのケアプランを作成していく必要があります。
居宅ケアマネと利用できる担当数に違いがあるのは、施設ケアマネの場合、他の事業者との連携や訪問などの手間が省けるため、多くの利用者様を支援できるといった理由です。
ケアプランを作成する前の、モニタリングなどもケアマネが行う施設も多いですが、直接支援している介護士や看護師に情報を収集することも多いです。
施設内でカンファレンスの開催
施設ケアマネの場合、ケアプランの更新は6ヶ月に1回となっています。
そのため、ケアプランの更新時に、ご家族に連絡し、カンファレンスの参加を促します。
参加できない場合は、施設内の各部署の担当者でカンファレンスを行います。
カンファレンスは、家族様やご利用者に今後どのように支援をしていくのかを伝えることと、利用者様の現状をお伝えする大切な会議です。
カンファレンスで、普段ご家族が聞けないことや、職員がご家族に伝えたいことを話し合う必要があります。
カンファレンスで、話しやすい雰囲気をつくることはケアマネの仕事です。
開催に合わせて、伝えたいことをまとめるなど事前準備が必要です。
介護業務との兼務
施設ケアマネの場合、利用者様1人に対して、6ヶ月に1回のケアプランの作成や見直しで良いことと、訪問や他事業所と繋げることがほとんど無いことから、時間に余裕があります。
施設によっては、介護職と兼務ではなく、相談員などと兼務しているケアマネもいます。
施設の方針や働き方によっても違いますが、兼務して働いている方が多くいらっしゃるのも事実です。
普段は、介護職や相談員として仕事を行い、空いている時間を見つけて、ケアプランの作成やカンファレンスの参加をすることがあります。
兼務は大変そうなイメージもありますが、メリットもあります。
介護職として、利用者様と直接関わると、より深く利用者様のことを知ることができるので良いケアプランを作成できます。
また、介護職や相談員ではご家族と関わる機会も増えるため、信頼関係が築きやすくなります。
余裕が無い時に、無理に兼務をすることは避けないといけませんが、ケアマネ業務が落ち着いている時は、積極的に利用者様やご家族と交流を深めていくことが必要です。
居宅ケアマネと施設ケアマネの働き方の比較
ここでは、居宅ケアマネと施設ケアマネの働き方の違いを表で見てみましょう。
給与は一概にどちらが良いとは言えません。施設ケアマネの場合、介護職と兼務することで「処遇改善手当」「夜勤手当」がつく場合があります。
| 居宅ケアマネ | 施設ケアマネ | |
|---|---|---|
| 勤務時間 | 日勤帯 | 介護職兼務の場合、早出・遅出・夜勤あり |
| ケアプランの作成 | 居宅ケアプランの作成 | 施設ケアプランの作成 |
| 担当件数 | 42.7件 ※令和4年度介護事業経営概況調査結果より | 〜100件程度 |
| サービス担当者会議の開催(カンファレンス) | 外部サービス(利用中・利用予定)に声をかけて、主となって開催 | 施設内の職員とご家族に声をかけて、施設内で開催 |
| 訪問頻度 | 1ヶ月に1回、利用者様のご自宅への訪問が必要 | 施設内の居室へ訪問し、状態を把握する必要があるが、義務ではない |
| 給付管理 | サービス事業所からくる前月分の実績を月初に入力し、国保連に請求する必要がある | 外部のサービスを利用した場合は、計算する必要があるが、特養などの入所サービスのみの場合は不要。 事務員が行っている場合が多い |
| 働き方 | 事業所により、直行直帰できる場合もある。 テレワークを導入する事業所もあり | 施設内での仕事がメイン |
| 認定調査 | 認定調査員として、ご自宅へ認定調査をすることがある。 | 認定調査の立ち会いがメイン (利用者様の状況を、調査員に伝える) 認定調査員の資格を取ると、施設内の利用者様の認定調査ができる場合もある。 |
居宅ケアマネと施設ケアマネに求められるスキルの違い
居宅ケアマネと施設ケアマネとでは、求められるスキルにも違いがあります。
仕事をする上ではどのスキルも大切ですが、より重視したいスキルをここでは解説していきます。
居宅ケアマネに必要なスキル
分かりやすく説明する技術
介護保険は複雑で分かりづらいことがたくさんあります。
ケアマネの仕事をしていても、「これどういう意味?」と思うことが多々ある中で、自分で理解し、利用者様、ご家族へ説明しなければいけません。
慣れてくると専門用語をたくさん使ってしまいがちですが、利用者様、ご家族へはできるだけ専門用語を使わずに伝え、分かりやすく説明する技術が必要になります。
ケアマネには「説明責任」というものがあります。ケアマネは説明した、と思っていても実際に伝わっていない、ということがないようにしていきましょう。
自己研鑽
介護保険制度は3年に1回改正があります。
居宅ケアマネは、自分に関係のあるところだけを確認しておくだけでなく、利用者様に不利益を与えないためにも、利用するサービスのことも確認しておく必要があります。
また、居宅ケアマネの場合、利用者様から医療保険のことや障害サービスのこと等を聞かれることもあり、介護保険以外のことでも調べたり、問い合わせをしたり、担当利用者様の疾患の知識、薬の知識等医療面の知識が必要になってきたりと日々、自己研鑽がかかせません。
自己管理力
居宅ケアマネは、ケアマネごとに担当利用者様がつくため自分の担当ケースをしっかりと管理していかなければいけません。
ケアマネの管理不足でケアプランの期間が切れていた、介護保険の更新手続きをし忘れていた、なんてことが実際に起こっていると聞いたことがあります。
ケアプランがなければ、利用者様はもちろん、サービス事業所へも迷惑をかけてしまうことになります。
また、日々の予定を管理をしっかりとしておかなければ、モニタリングにいく時間がなかった、書類を期限内に送っていなかった、という事態を招く可能性があるため、しっかりと自分で予定を管理することも求められます。
施設ケアマネに必要なスキル
自分の価値観を知る
施設ケアマネは、居宅ケアマネとは仕事内容が大きく異なります。
施設内で完結することも多く、利用者様もコミュニケーションが取れないというケースが多くあります。
その際に、施設の職員やご家族と相談しながらケアプランを作成しますが、ニーズの把握が充分にできないことや、外出などの支援をしたくてもできないといったことが起こります。
そういった中での、目標設定は非常に難しく、施設内の利用者様が同じようなケアプランに偏りがちになります。
「個別性」であるべきはずのプランですが、同じようなケアプランをずっと続けているといった状況が多くあると聞きます。
そうならないためにも、施設ケアマネ専用の研修会に参加したり、ケアプランのモニタリングや評価の際に、他の専門職の方に意見を聞き、誰が見ても「その利用者様のケアプラン」と分かるようなプラン作成を心掛ける必要があります。
このスキルは、普段から一人一人に向き合い、経験を積んでいくことで身につけることができるでしょう。
コミュニケーション力や調整力
コミュニケーション力は、どのような職種でも必要とされていますが、施設ケアマネの場合、コミュニケーション力に加えて、施設で利用者様が住みやすく、職員が働きやすい職場とするために、調整力が必要です。
ケアマネが中立であることは、施設ケアマネでも同様です。
看護師の意見や介護士の意見など、色々なことを耳にする機会が多いと思いますが、どちらか一方に偏ってはいけません。
利用者様、ご家族、看護師、介護士、相談員、栄養士、ケアマネの意見をまとめて、みんなが納得する形にしないといけません。難しい場合は、自分の意見を伝えつつ、理由を述べた上で、支援が難しいことを伝える必要があります。
このような、コミュニケーションと調整を繰り返していくことで、「信頼できるケアマネ」として周りも助けてくれるようになります。
忙しい中でも、コミュニケーション力や調整力はしっかりと身につけることが必要です。
施設支援の中心を担っていることを自覚する
施設ケアマネは、兼務することもあり、日によって立場が変わることがあります。
その際に、「自分は本当はケアマネなのに」と思いながら、介護の仕事をしている方も多いと聞きます。
ケアマネという役職を持っていても、あくまでも「施設の利用者様の生活をより良くする」という目的は、どの職種でも一緒です。
自分の立場は関係なく、今目の前の仕事に集中していくことが大切です。
施設では、利用者様の最期を見送る為の「看取りケア」を取り入れていることもあります。
その際の、看取り計画書は、ケアプランとは違いますが、積極的にプラン作成に関わっていき、できる限り、利用者様が苦しまず、ご家族の後悔が無いようにする支援が必要です。
「介護職の仕事だから」とか「相談員がご家族に連絡すべきだ」という、固定観念に囚われずに、自身がケアマネとして、時には、介護士として施設支援全体の中心を担っているといった気持ちで仕事をする必要があります。
居宅ケアマネと施設ケアマネ、どちらで働くか迷ったときの選び方
これまで見てきたように、居宅ケアマネ、施設ケアマネはそれぞれ働き方や必要なスキルにおいて共通する部分もありますが、それぞれの違いも見えてきたかと思います。
どちらもメリット、デメリットがあり、どちらがよいのかは、ご自身の理想とする働き方やどのような仕事をしたいのかで変わってきます。
ケアマネとして、例えば以下の視点で考えてみるのはいかがでしょうか。
- 介護が必要になった高齢者の在宅での生活を支援したいのか
- 施設での生活を支援したいのか
- 施設の中でも老健で在宅復帰に向けての支援をしたいのか
- 特養で人生の最期の支援をしたいのか
このように、ご自身が利用者様のどのような支援をしたいのかを考え、選んでみてはいかがでしょうか。
まとめ
居宅ケアマネや施設ケアマネで働く際にはメリット・デメリットはありますが、どちらが自分に向いている働き方であるのかを考えるきっかけになったのでは無いでしょうか?
自分に向いている方はどちらかを考えることももちろん大切ですが、どのような環境で働くかも非常に重要です。
例えば、居宅ケアマネでも時間に融通が利く職場やリモートを取り入れている職場では、働きやすさは変わってきます。
また、施設ケアマネであっても他の職種との兼務無しでケアマネ業務に集中できるという職場もあります。
環境が良ければ、居宅ケアマネでも施設ケアマネでも充分な経験が積めますし、何よりケアマネの仕事が楽しいと思えるでしょう。
居宅ケアマネか施設ケアマネどちらで働くか迷ったり、どのような職場で働きたいかが分からない場合は、ぜひ一度「ケア人材バンク」にご相談ください。
「ケア人材バンク」では、ケアマネや相談員、障がい福祉専門の転職支援サービスを行っています。
ケアマネ専門の担当者も多く在籍しており、無料で転職支援も行っています。ぜひこの機会にご登録ください。
※当サイトで提供される情報は、一般的な情報提供のみを目的としており、専門家による助言に代わるものではありません。特定の状況に関するアドバイスや支援が必要な場合は、必ず専門家にご相談ください。