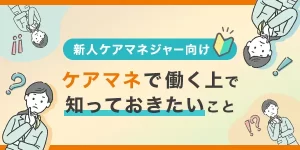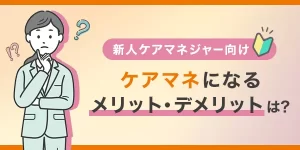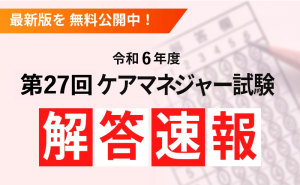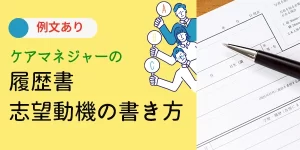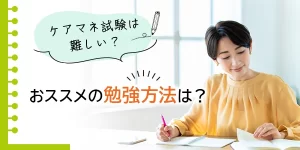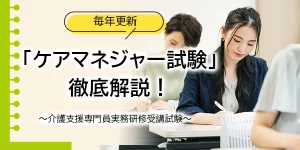ケアマネジャーの仕事の中で、重要でかつ一番頭を悩ませるのがケアプランの作成になります。
利用者様やご家族、事業所などが、ケアプランを通して支援を行います。
ケアプランは、様々な方が利用者様の支援に関わる中で、共通認識をもってもらえるようにする役割があります。
利用者様や支援者がみんな同じ方向を向くことでより、充実したサービスの提供ができるでしょう。そのためにも、ケアプランの作成は非常に重要です。
ここでは、ケアプランの計画から作成までの流れを分かりやすく解説していきます。
目次
ケアプランとは
ケアプランの目的
ケアマネジャーの仕事の一つに、ケアプランを作成することがあることは皆さんご存じかと思います。
では、ケアプランの目的とは一体何でしょうか?
ケアプランの目的を知ることで、ケアプランの理解をより深めることができるでしょう。
共通認識を持つことで、みんなが同じ方向を向いて支援できる
ケアプランは、利用者様の生活状況や環境などに配慮し、これから生活していく上で利用者様が望む生活を実現できるように支援の計画を立てることです。
利用者様一人一人、病状や性格、歩んできた過去、取り巻く環境(ご家族や友人・親戚など)などは違っています。
そんな中で、より最適な選択を考え、望む生活を実現できるように支援するためケアプランがあります。
このケアプランは、利用者様の支援の指針となるものです。
支援者がケアプランに沿って支援をすることで、みんなが同じ方向を向いて利用者様を支援することができるのでとても重要なものです。
また、利用者様自身やご家族に対しても、「このようなニーズがあるので、このように支援を実施しています」となぜこのサービスを受けているのかを確認することができるのです。
支援者の指針である、ケアプランは誰が見ても分かるように記載する必要があることと、ケアプランを作成するのは、ケアマネジャーですが、あくまでもチームで支援しているという認識が大切です。
直接援助するご家族や事業者の意見を聞くことと、利用者様が何を望んでいるのかを正確に把握し、ケアプランに反映させることで、みんなが同じ方向を向いて支援できるのでより良いサービスが提供できます。
利用者様が望む生活の実現に役立つ
ケアプランは、「どのように生活し、生きていきたいか」という人生プランの設計をするために用いられます。
人は誰しも、生きていく上では課題を抱えています。その課題がニーズであり、そのニーズを解決していくために目標を設定します。
しかし、同じような毎日を繰り返すうちに、「なぜ自分はこのサービスを利用しているのか」など、ニーズや目標を忘れることがあります。
また、利用者様の状態が変わることで、課題や目標の変更は定期的にあります。
そのために、ケアプランとして実際に書面で書き残し、利用者様やご家族と確認をすることで、「こういう課題があったな」「この目標達成に向けて頑張ろう」と思えるのです。
このモチベーションを維持するために、ケアプランは必要です。利用者様が良い方向へ状態が変化すると、生活する意欲が沸いてきます。ご家族や周りの環境にも良い影響となります。
適切なサービス提供につながる
介護度に応じて、介護保険でのサービスを利用できる単位が決まっています。
要介護5であるから色々なサービスを入れようと考えるかもしれませんが、サービス提供だけが利用者様の自立支援を促すことには繋がりません。
この課題を解決するためには、このサービスが必要だというしっかりとした根拠を持って提供するサービスを選ぶことが必要であるとともに、利用者様やご家族に説明する責任もあります。
また、ケアプランには、介護保険以外のサービスについても記載する必要があります。
例えば、
- 公民館での食事会、認知症カフェ
- ご家族の支援
- 民生委員の見守りサービス
など、不定期であっても、利用者様を支援する一員であることには変わりありません。
そういった、支援も把握した上で、必要なサービスを選び提供するといったことが大切です。
そのために、ケアプランに漏れなく支援内容を入れ込むことで、過剰なサービスの提供などを防ぐことができます。
ケアプラン作成の流れ
ケアプラン作成の前に、市町村に申請し、介護保険証を交付をしてもらい、専任のケアマネジャーを決める必要があります。
ケアマネジャーが決まって、面談などを重ねていく上でケアプランを作成していきます。
ここでは、ケアプランを作成する際は、どのような手順で作成していくかを詳しく解説します。
実際に、ケアプラン作成の流れを知ることで、ケアプランの立て方を具体的にイメージできると思います。
アセスメント
ケアプランを作成する上で最も重要なことが、「情報収集」です。
「アセスメント」とも呼ばれており、利用者様の現在の状況や過去の生活歴、病気、性格、周りの人間関係や現在おかれている状況などを詳しく聞き取る必要があります。
主にアセスメントシートを用いて順番に聞き取りをしていきますが、聞き取り項目にない項目は、例えば、以下のようなことも記載する必要があります。
- 利用者様の表情や仕草
- 口調
- ご家族との意見の違い
- 生活環境
利用者様は、ケアマネジャーの前で話ができないことや、強がったりすることもしばしば見受けられると聞きます。
このアセスメントを、より正確に記載していくには、「信頼関係の構築」が必要です。
信頼がない相手に、自分のことを全てさらけ出せる方は少ないので、初回の面談を通して、徐々に距離を縮めながら情報収集をする必要があります。
急いでアセスメントを取ってしまうと利用者様の潜在的なニーズが把握できず、ケアマネジャーと利用者様の間でのニーズの相違が起こってしまいます。
そうなってしまうと、いくらサービスを提供しても、利用者様のモチベーションや生活状況は変わらず信頼も構築されません。
アセスメントをする際には、記入することばかりに意識がいくことがないように、実際に利用者様の顔を見ながらゆっくりと情報を収集していくことが重要です。
ケアプラン原案作成
アセスメントシートで、ある程度ニーズが把握でき、必要なサービスをイメージできたら仮のケアプランを作成します。
ここで作成するのは、あくまでも仮のケアプランということです。
ケアプランは、ケアマネジャーだけで作成するものではありません。
他のサービス事業所の意見を聞くとともに、サービスの提供が可能かどうかも確認が必要です。
ニーズや目標を設定し、サービス事業者を利用者様やご家族と決めて納得した上で、仮のケアプランを作成し、担当者会議でサービス提供事業者に仮のケアプランを配ります。
その際、どういう経緯でこのサービスが必要なのかということもしっかりと説明することが大切なので、支援経過などに、初回の面会時からの様子などを記載しておくと良いでしょう。
また、基本情報を記載したフェイスシートや週間サービス計画書等も準備し、配布できるようにしましょう。
担当者会議
担当者会議でのケアマネジャーの役割は主に以下の通りです。
- 関係者の選定・声掛け
- 出欠確認
- 会議のファシリテーター
- 情報共有を行い、具体的な意見を引き出す
担当者会議は、利用者様を支援する事業所や時には医師まで声かけをして、出席してもらいます。
業務が多忙な中で集まるということで、ケアマネジャーはスムーズに進行できるように準備をしておく必要があります。
まずは、担当者会議をどこで実施するのかを検討する必要があります。
多くは、生活の環境などを見てもらうという目的もかねて、利用者様の自宅に集まることが多いですが、利用者様の自宅が厳しい場合は、事業所の会議室や相談室で実施する場合もあります。
日時と場所と話し合う議題を事前にサービス提供事業所に連絡し、出欠の確認を取ります。
欠席の場合は、担当者会議照会という書面を送り、書面にて意見を記載してもらいます。
担当者会議は、利用者様やご家族、事業所が顔を合わせる数少ない機会となります。
この担当者会議を有意義なものにすることが、良いケアプラン作成へとつながっていきます。
支援する方の中でも、医療職や介護職、リハビリ職など他職種の方が関わってきます。
そういった方の意見や助言を踏まえながら、利用者様自身が真の気持ちを表現できるように、また利用者様本人の意向に沿う形で調整していくことが大切です。
目標設定
ケアプランを作成する際の目標の設定は、達成できるものでなくてはいけません。
そのため、目標達成に向けたサービスの内容になっているのか、各サービス事業所の特性を理解した上で確認が必要です。
短期目標と長期目標は連動していることが大切です。
例えば以下の通りとなります。
- 長期目標「自宅内を手すりを持って歩ける」
- 短期目標「自宅内の寝室からトイレまで手すりを持って歩ける」
短期目標の達成を目指し、長期的にこのようになりたいという利用者様の意向に合わせていく形となります。
サービス内容の調整
ケアプランを作成してみて、目標やサービス内容が分かりやすく、また実現可能なものとなっているかの調整を重ねていく必要があります。
これらを各事業所に確認をしていきながら、モニタリングへと繋げていく必要があります。
- サービスが計画通り適切に実施されているのかどうか
- 利用者様の状態の変化
- サービス実施上の問題が生じてないか
- サービス利用上の注意点の共有
また、ケアマネジャーも、サービス提供の一員であり、適切なタイミングで介入していきます。
以下のように、報告を受けるだけではなく、実際にケアマネジャーが自宅へ足を運んで状況を把握していくことが大切です。
- トラブルの報告を受けたら、利用者様から話を聞いたり、事業所各所と連絡を取る
- 日々、利用者様の状態の変化や表情の違いを把握
- 利用者様の周りの環境に変化はないか、主の介護者に疲れはないか
ケアプランの文例集
ケース例1.脳梗塞を発症後、リハビリ病院入院を経て自宅療養
要介護2の男性。妻、長女家族と同居。
左半身に軽度麻痺がある。認知機能に問題なし。
病院では多点杖や手すりを使用することで、見守りのもと一人で移動可能。
入浴は排泄は、一部介助。デイケアでリハビリと入浴、福祉用具貸与を利用。
文例① 利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果
利用者:家族に迷惑をかけたくない。少しでも、自分でできることは自分でしたい。
家族:リハビリをして、今の状態を維持してほしい。
課題分析結果:利用者及び家族の意向を踏まえ、リハビリをすることで心身機能の低下を 予防し、日常生活動作が維持出来るようにしていく。
文例② 総合的な援助の方針
リハビリを継続しながらご自身でできることを増やし、身体の状態を維持していきましょう。また、適切な福祉用具を活用することで、安全に生活できるようにしていきましょう。
主治医:〇〇クリニック 〇〇先生 〇〇〇ー〇〇〇〇
緊急連絡先:〇〇 〇〇様(長女様) 〇〇〇ー〇〇〇〇
文例③ 生活全般の解決すべき課題(ニーズ)/長期目標/短期目標
- トイレで排泄したい/手すりを活用しトイレで排泄できるようになる/見守りのもとトイレで排泄できるようになる。
- 家の中を自分の足で移動したい/家の中を自分の足で歩けるようになる/見守りのもと多点杖で歩けるようになる
- 安全に入浴したい/安全な環境のもと入浴できる/身体に合った入浴動作を身につける
- 他人と交流し、話をしたい/家族以外の他人と話す機会を作る/他人と交流する場所へいく
ケース例2.独居。アルツハイマー型認知症と診断
要介護1の女性。一人暮らし。
半年前にアルツハイマー型認知症と診断された。
長男家族は車で30分ほどのところに住む。
できることは手伝いたいが、長男夫婦とも仕事があり、何かあってもすぐに対応することは難しい。
一人で買い物へいくと同じものを買ってきたり、薬の飲み忘れ等はあるが、他のことはおおむねできている。
デイサービス、訪問看護、訪問介護を利用
文例① 利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果
利用者:絵手紙や手芸をすることが楽しみ。みなさんにとてもよくしてもらっているので、これからもよろしくお願いします。
家族:家での生活が難しくなれば、施設入所も検討しています。それまで、皆様に助けてい ただきたいです。
課題分析結果:利用者及び家族の意向を踏まえ、好きなことを続けながら、安心して在宅生活を送っていけるようにする。
文例② 総合的な援助の方針
絵手紙や手芸などの楽しみなことを続けながら、安心して自宅での生活を続けていきましょう。
主治医:〇〇クリニック 〇〇先生 〇〇〇ー〇〇〇〇
緊急連絡先:〇〇 〇〇様(長男様) 〇〇〇ー〇〇〇〇
文例③ 生活全般の解決すべき課題(ニーズ)/長期目標/短期目標
- 絵手紙や手芸をしたい/絵手紙や手芸を楽しむ/絵手紙や手芸を安全に行うことができる
- 薬を忘れずに飲みたい/薬を忘れずに飲む/専門職による声かけのもと服薬確認を行い、飲み忘れを防ぐことができる
- 清潔な環境で生活したい/定期的に掃除する/ヘルパーと一緒に掃除する
- 昔からの友人と会いたい/長年行っている老人会へ参加し友人と会い交流する/老人会に参加する
ケアプランの重要性
ケアプランは何故必要なのでしょうか?
介護保険制度が施行され、サービスの自由化により、サービス提供事業者が多く誕生しました。
利用者様やご家族がそれぞれのご家庭のニーズに合わせてサービスの選択がしやすくなりました。
しかし、あまりにもサービスが多いため、「どのサービスを選んだら良いか分からない」と言った状況にも陥ってしまいました。
そこで、ケアマネジャーと共にサービスを選択することで、効率的で効果的なサービス提供が実現できます。
ケアプランの重要なポイントは、以下の点が挙げられます。
- 利用者様の自立の支援
- 必要なサービスの選定を行い、自立支援に繋げる
- 具体的で分かりやすい目標の設定(数値を用いて達成状況を分かりやすくすると良い)
- 他事業所の支援の指針となる
- 生活状況の改善
- 利用者様やご家族、友人などとの関係の構築
ケアプランに沿って、利用者様の状態の把握もすることができ、必要のないサービスを変更して、必要なサービスに切り替えるといった判断も早くでき自立支援に繋げられます。
また、支援者にとってもサービス提供の指針となり、「歩きたい」というケアプランのニーズがあれば、「歩けるようにするため、このようなリハビリを行っていく」というケアプランに連動した個別計画書を立てることができます。
そして、介護保険の利用をきっかけにご家族や友人と連絡を取り、関係を再構築することも大切です。「孫とよく会えるようになった」と元気を取り戻した方もいらっしゃると聞きます。
ケアプラン作成後のモニタリング
モニタリングとは、ケアプラン通りの介護サービスが適切に提供されているか、利用者様、ご家族のニーズに合っているかを定期的(おおむね月に1回)に確認することです。
例えば以下のような点を確認します。
- 訪問介護や通所介護、福祉用具貸与等の介護サービスが、ケアプラン通りに提供されているか
- ケアプランの目標の達成状況
- 困り事や要望に変化がないか
- 利用者様やご家族がサービスに満足されているか
確認後、ケアプラン通りにサービスが提供されていなかったり、利用者様やご家族がサービスに満足されていなければ、サービス事業所とすり合わせしたり、困り事や要望が変わった場合、ケアプランの目標に変化がある場合等はケアプランの見直しを行います。
モニタリングでは、利用者様、ご家族が実際にどのように思っているのか、本心を確認することが大切になります。
本心を話していただけるように利用者様やご家族に話しやすいと思ってもらえる関係を作ること、利用者様やご家族の表情から読み取る力、言いたいことを代弁する力が必要になってきます。
まとめ
ケアプランの具体的な計画作成方法をイメージできましたか?
最近では、システムでケアプランを作成している事業所がほとんどだと聞きます。
システムでは、過去の目標やニーズ、サービス内容などが反映されており、同じ文面を使用できるようになっています。
しかし、ケアプランはお一人お一人違うものとなります。
例え同じ病気であっても、利用者様の状況や環境、悩みや価値観はそれぞれ全く違うものであるということは覚えておかなければいけません。
利用者様の潜在的なニーズも含め、利用者様に寄り添った計画である必要があります。
今では、ニーズの書き方としても、利用者様が話をしたことをそのまま入れ込んで、より具体的で分かりやすく記載しているところもあると聞きます。
「外に出かけたい」という書き方ではなく、「天気良いし、外に出て花とか見に行きたいなぁ」と言った言葉をそのまま変えずに書くということです。
利用者様の馴染みのある言葉で記載することにより、自分自身のために立ててくれたケアプランという認識が強くなります。
ケアプランは、利用者様や支援者に分かりやすく伝われば、書き方の統一などはありません。
上手く書こうとしなくても大丈夫です。そのことを意識しながら、利用者様がケアプランを身近に感じてくれたら、良いケアプランとなるでしょう。
ケア人材バンクでは、ケアマネや相談員、障がい福祉専門の転職支援サービスを行っています。
ケアマネ専門の担当者が在籍しており、無料で転職支援が受けられます。
ケアマネジャーで働いて、利用者様に寄り添ったケアプランを作成し、経験を積んでいきたいという方は、是非一度ケアマネジャー専門の転職エージェントにご相談ください。
※当サイトで提供される情報は、一般的な情報提供のみを目的としており、専門家による助言に代わるものではありません。特定の状況に関するアドバイスや支援が必要な場合は、必ず専門家にご相談ください。