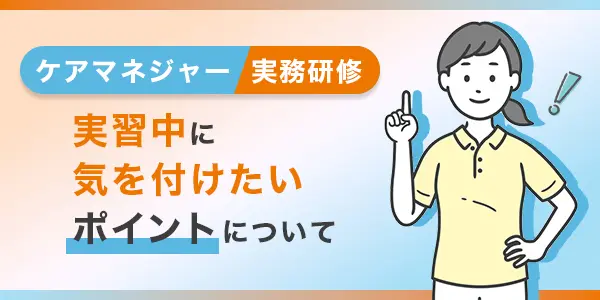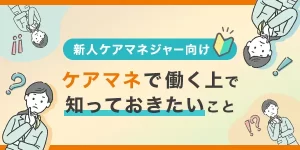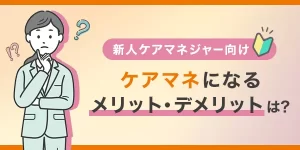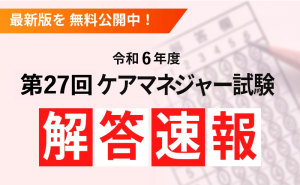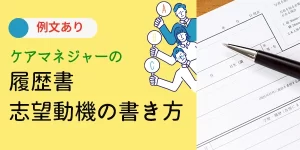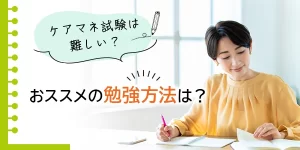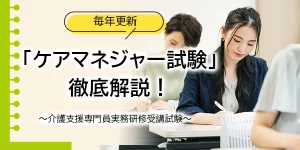ケアマネジャーになるには、試験に合格するだけでなく、実務研修を受講する必要があります。実務研修には前・後期合わせて計87時間の講義があり、実習は前期と後期の間に、3日程度行うようカリキュラムに含まれています。
これから研修を受講する方のなかには、実習の詳細がわからず、不安に思っている方もいるのではないでしょうか。
本記事ではケアマネ実務研修の履修に必要な実習の具体的な内容や準備のポイントに加えて、実習を実務に活かすための取り組み方についても解説します。
実務研修の実習について理解したい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
ケアマネ実務研修 実習前の準備で心がけること
ケアマネ実務研修の実習は、前期研修の終了後から後期研修が始まるまでの間に行います。
そのため、実習が履行できなかったり、提出書類に不備があったりすると、後期の研修が受講できなくなるため注意が必要です。
実習の実施方法は自治体によりさまざまですが、以下の情報は確認しておくとよいでしょう。
実習前に知っておくべきこと
実務研修の実習前に知っておくべきことは、実習の目的とカリキュラムです。
実習の目的は2つあります。
- 前期研修で学んだアセスメントやケアプランの作成といった一連のケアマネジメントプロセスを実践し、理解すること
- 利用者様の自宅への訪問や担当者会議へ参加することで、利用者様ごとの生活の多様性を理解すること
また、実習のカリキュラムには、見学実習のみ行う自治体と、ケアプラン作成実習も行う自治体があります。
以下の表にそれぞれの概要をまとめたので参考にしてください。
| 見学実習 | ケアプラン作成実習 | |
|---|---|---|
| 内容 | 実習先において、実習指導者(主任介護支援員)が行うケアマネジメントプロセスを見学する | 要介護状態にある人(実習協力者)に協力してもらい、実際にケアプランを作成する |
| 実習時間 | 3日間程度 (日数や1日の実習時間は自治体により異なる) | 規定はないが、実習協力者との面談時間や、書類作成の時間が必要 |
| 実施時期 | 前期研修と後期研修の間 (順序は問わない) | |
| 実習先/協力者の選定 | 研修の運営先で選定 | 実習生が自ら確保する (自治体により調整可能な場合もある) |
出典元:介護支援専門員養成研修における実習受入に関する指針(厚生労働省)
実習の具体的な実施方法は各自治体によって異なるため、研修の手引や実習オリエンテーションでの指示をよく確認してください。
実習スケジュールの把握と、実習時間の管理
ケアマネ実務研修の実習は、前期研修終了から後期研修開始までの1~2ヶ月程度の期間内に完了させる必要があります。
見学実習の実習先は研修の運営元で調整してくれるケースが多いですが、実習の日程は自分で調整しなくてはなりません。
ケアプラン作成実習の場合は、協力者の選定から自分で行うため、より時間がかかってしまいます。
また、見学実習は、3日程度とされていますが、実習先によっては必要な時間数を複数回に分けて実施する場合もあります。
自治体によって実習の日数や時間数も異なるため、よく確認したうえでの調整が必要です。
さらに、実習中は実習記録や報告書など、多くの書類を作成・提出する必要があります。
書類作成の時間も考慮して期日に余裕のある実習スケジュールを立てるのがポイントです。
体調管理
実習中の体調管理には特に気をつける必要があります。
体調不良が理由であっても、実習時間や提出書類を免除されることはありません。
実習先や協力者への配慮としても、体調管理は重要です。
外出時のマスクやうがい、手洗いなどの感染予防対策に加え、規則正しい生活や栄養バランスのとれた食事を心がけましょう。
万一、実習中に体調が悪くなった場合は、速やかに実習先や研修実施機関に報告し、指示を仰ぐようにします。
実習の免除は不可能ですが、日程を変更してもらえる可能性はあります。
ケアマネ実務研修 実習中に意識したいポイント
ここでは、実習中に意識したいポイントについて、以下の3点を解説します。
- 現場での報告、連絡、相談
- 上司や先輩、指導者とのコミュニケーション
- 利用者様、ご家族との関わり
ひとつずつ解説します。
現場での報告、連絡、相談
ケアマネジャーの実務において、利用者様やご家族、その他の関係者との報告・連絡・相談(ホウレンソウ)は業務の基本となります。
実習中とはいえ、指導者との密な情報共有が求められ、これは将来のケアマネジャーとしての基礎となる重要なスキルです。
実習中は、挨拶は当然のこと、指導や助言を受けたことはしっかりメモを取るようにします。
そして、日々の業務開始時と終了時に必ず指導者への報告を行います。
特に利用者様の状態変化や気になる点は、些細なことでもその場で報告することが重要です。
また、わからないことがあれば、その場で質問することで、より深い学びにつながります。
実習記録は、実習で学んだこと、気づいた点、疑問に感じたことなどを具体的に記載します。
これらの記録は、後の振り返りや学習にも活用できる貴重な資料となるでしょう。
上司や先輩、指導者とのコミュニケーション
実習期間中、指導者との良好なコミュニケーションをとれるかによって、実習の学びの質は異なります。
基本となるのは、マナーを守り、専門職としての態度を示すことです。
質問する際は、事前に自分で調べてから行うことで、より深い理解につながります。
また、指導者は自身の業務をしながらの指導となるため、質問はまとめてするといった、効率的なコミュニケーションを心がけるとよいでしょう。
実習目標については定期的に指導者と共有し、進捗を確認することが大切です。
指導者からのアドバイスには謙虚に耳を傾け、実習中の気づきや学びを積極的に共有することで、より充実した実習となります。
利用者様・ご家族との関わりについて
実務研修の実習において、利用者様やご家族との関わりは最も重要な学びの機会です。
ケアマネジャーとして働きはじめると、先輩が直接利用者様やそのご家族と関わるところを見る機会はあまりありません。
そのため、身だしなみや言葉遣い、立ちふるまいなど、実習の機会によく観察しておくことが大切です。
利用者様との面談では、相手の体調や意向に十分配慮しながら聞き取りを行います。
特に初回の面談では、ご家族の立ち会いを依頼し、家族関係や生活環境についても理解を深めるよう意識します。
ただし、答えたくない事項については無理な聞き取りを避け、利用者様の意思を尊重することが大切です。
面談時は個人情報保護と守秘義務を徹底し、専門職としての信頼関係構築に努めます。
他職種との連携に注目する
ケアマネジャーの役割のひとつは、他職種連携のコーディネート役として連絡調整を行うことです。
実習中は、サービス担当者会議の準備や同席を通じて、実際の連携の場面を学ぶ機会になります。
社会状況の変化により、利用者様が抱える問題は複雑化しています。
医療職との連携方法や、各専門職の役割と責任範囲を理解する貴重な機会です。
情報共有の方法や多職種間での意見調整の実際の現場を観察し、チームアプローチの重要性を実感できます。
課題を解決するためにどのような情報共有ツールを活用しているか、効果的な会議の進め方など、実践的なスキルに注目できると良いでしょう。
これらの経験は、将来のケアマネジャーとしての業務に直接活かせます。
ケーススタディの実践と記録の重要性
ケーススタディは、実際の事例を分析して、課題解決に役立つ方法を検討する手法で、事例研究とも呼ばれています。
ケアマネジャーの実習において、ケーススタディの実践と記録は学びの核となる要素です。
ここでは、それぞれの重要性について解説します。
ケースごとの課題解決方法の考察
ケーススタディでは、利用者様の状態把握から支援計画の立案まで、実践的なスキルを学びます。
具体的には、ひとりの利用者様の全体像を把握するため、医療面、生活面、社会面など、多角的な視点からアセスメントを行います。
また、利用者様の強みを活かしたアプローチを考え、家族支援の視点も含めた包括的な支援計画を立案することも大切です。
脳血管疾患や認知症、大腿骨骨折など、高齢者に起きやすい疾患の特徴を整理しておくことも大切です。
これらの疾患を抱えている方に対して、どのように課題解決に向けたアプローチしているかという点に注目するとよいでしょう。
具体的な目標設定と、計画の進捗を評価するモニタリング方法を学ぶことで、より実践的な課題解決能力を身につけられます。
記録を正確に残す方法
実習中、書類作成に悩まされる実習生は多いです。
記録作成はケアマネジャーの重要な業務なので、正確かつ効率的に記録できるよう、前向きに取り組めるとよいでしょう。
事前に必要な書類を確認し、何を記録するのか把握しておくことが大切です。
5W1Hを意識して、客観的事実と主観的な意見を区別して記録します。
また、時系列での記録を心がけ、専門用語の使用方法が正しいか確認しながら記録します。
個人情報保護の観点から、記録の取り扱いには細心の注意を払うことが大切です。
参考にできるお手本があると記録が楽になります。
実習指導者が作成した記録の閲覧をお願いするのも良いでしょう。
また、記録方法についての書籍や、インターネットで公開されている例文など、参考にできる資料を探してみるのも一案です。
実習後にやっておきたいこと
実習での経験を続く後期研修や今後の実践に活かすために、実習後は振り返りが重要です。
振り返ることで学びが定着し、指導者からのフィードバックを活用することで、実務に向けた準備を進めやすくなります。
実習の振り返り
実習で得た学びを定着させるには、振り返りが有効です。
実習ノートや記録を活用し、行ったこと、気づいたこと、指導を受けたことなどを整理することで、将来の実務に活かせます。
振り返りでは、日々の実習での気づきを整理し、成功体験と課題を明確化します。
特に、利用者様との関わりから学んだことや、多職種連携で気づいた重要なポイントは、具体的に文書化しておくとよいでしょう。
また、実習前に立てた目標の達成度を確認し、自己の強みと弱みを分析することで、今後の課題が明確になります。
後期の研修では実習を振り返り、他の実習生と共有する時間が設けられています。
他の実習生の体験も共有することで、よりいっそう学びを深められるでしょう。
復習の重要性
実習期間中に学んだ内容を確実に身につけるためには、計画的な復習が重要です。
特に、制度やケアマネジメントの一連のプロセスなど、実務の基礎となる知識はしっかりと復習する必要があります。
具体的には、アセスメントツールの使い方や記録作成のポイント、面接技術などの実践的スキルを再確認します。
また、地域資源に関する情報や医療知識、介護保険制度についても理解度を確認し、必要に応じて再確認します。
実務で使用する書類の作成練習も、この時期に確認しておくとよいでしょう。
後期の研修でわからないところを他の実習生や研修指導者に質問するのもひとつの方法です。
研修期間中に実務で活用できる知識として定着させることが大切です。
指導者からのフィードバックの活用
実習指導者からのフィードバックは、実務に向けた貴重な資料です。
フィードバックの内容を具体的に文書化し、指摘された課題への対応策を検討することで、実務への準備を効果的に進められるようになります。
フィードバックされた評価内容を分析して、自己の課題を明確にし、具体的な行動計画を作成します。
指導者からの助言は、実務に向けた準備事項の確認や、今後の学習計画に反映させることが重要です。
また、実務経験豊富な指導者との関係性を継続することで、将来的なキャリア形成に関する相談もできます。
実務に就くと、自分の支援に対してフィードバックをもらう機会はそうありません。
実習指導者のコメントは大切に保管し、いつでも見返せるようにしておくとよいでしょう。
まとめ
本記事では、実務研修中に行われる実習の内容や、必要な準備と心構えなどについて解説しました。
実習は現場の雰囲気を体感できる貴重な機会でもあります。
主体的に取り組み、充実した実習にしてください。
実習をクリアして、実務研修を修了すれば、ケアマネの資格を取得でき、今より条件のよい会社に転職できる可能性が広がります。
「ケア人材バンク」では、専任のアドバイザーが、あなたの資格や希望条件などを考慮し、職場探しから入職までの転職活動をサポートします。
無料で利用できるので、まずは登録してみてはいかがでしょうか。
※当サイトで提供される情報は、一般的な情報提供のみを目的としており、専門家による助言に代わるものではありません。特定の状況に関するアドバイスや支援が必要な場合は、必ず専門家にご相談ください。