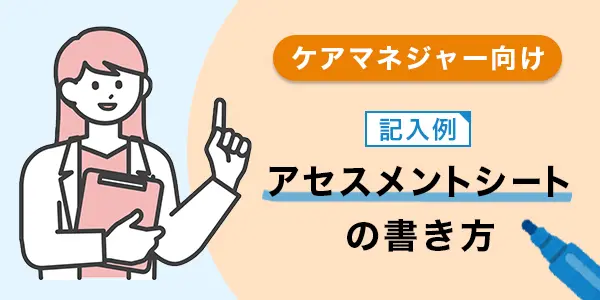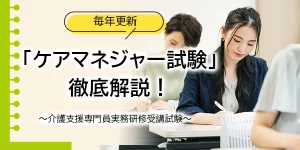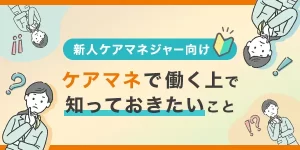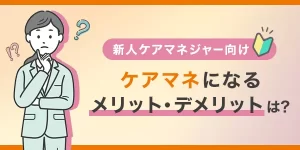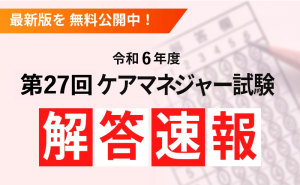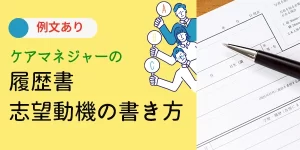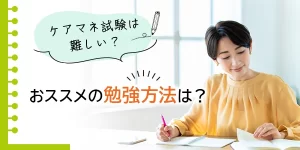ケアマネジャーにとってアセスメントは、ケアマネジメントのプロセスのなかでも特に大切な工程です。
しかし、「どのように情報を集めればいいのか」「利用者様のどこを見るべきなのか」など、具体的な進め方に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、アセスメントの重要性と適切な進め方、役立つツールや記入例について解説します。
アセスメントへの理解を深め、自信を持ってアセスメントに取り組むために、ぜひお役立てください。
ケアマネ・相談員
障がい福祉資格専門!
完全無料の転職エージェント
ご相談ください。
- 自分では良い求人を
判断できない… - 今より給料アップ
したい! - 自分に合う職場
を探してほしい
目次
ケアマネジャーのアセスメントとは?
ケアマネジャーがおこなうアセスメントは、利用者様の状態や環境に関する情報を収集・分析し、解決すべき課題を明確にするためのプロセスです。
アセスメントを通じて、利用者様一人ひとりに最適なケアプランを作成するための基礎となる情報を整理していきます。
アセスメントの役割と目的
アセスメントは、利用者様の望む生活を実現するためのプロセスです。
同じ介護度でも利用者様によってADLや生活環境、要望は大きく異なるため、全員同じようなサービス提供は適切ではありません。
アセスメントの主な目的は、利用者様の基本情報から人生背景までの情報収集、課題の明確化、そして利用者様・ご家族との目標設定です。
このプロセスを通じて、利用者様の生活課題を明確にし、ご本人の暮らしを支えるケアプラン作成に近づきます。
アセスメントに必要な課題分析標準項目
アセスメントでは、厚生労働省が示す23の項目(課題分析標準項目)を評価する必要があります。
具体的な内容は以下のとおりで、基本情報に関する項目(計9項目)と、課題分析に関する項目(計14項目)に分かれています。
- 基本情報(受付、利用者等基本情報)
- これまでの生活と現在の状況
- 利用者の社会保障制度の利用情報
- 現在利用している支援や社会資源の状況
- 日常生活自立度(障害)
- 日常生活自立度(認知症)
- 主訴・意向
- 認定情報
- 今回のアセスメントの理由
- 健康状態
- ADL
- IADL
- コミュニケーションにおける理解と表出の状況
- 認知機能や判断能力
- 生活リズム
- 排泄の状況
- 清潔の保持に関する状況
- 食事摂取の状況
- 口腔内の状況
- 社会との関わり
- 家族等の状況
- 居住環境
- その他留意すべき事項・状況
決まった書式はありませんが、上記の課題分析標準項目に関する情報を収集し、分生起する必要があります。
アセスメントシートの種類と選び方
介護支援専門員が使用するアセスメントシートには、課題分析標準項目(23項目)に基づいた複数の様式があります。
それぞれに特徴があり、利用者様の状況や事業所の特性に応じて適切な様式を選択することが重要です。
アセスメントシートの種類とその特徴
アセスメントシートは、医療・介護に関するさまざまな団体が開発しています。
施設サービスで多く使われているのは「包括的自立支援プログラム方式」で、要介護認定の際におこなう認定調査の項目と連動しているのが特徴です。
また、居宅介護支援事業所では「居宅介護サービス計画ガイドライン方式」が多く採用されています。
上記の他にも、老健向けのR4方式、インターライ方式など多くの様式があり、事業所が独自に作成しているケースも少なくありません。
アセスメントシートの選択方法
アセスメントシートを選択する際は、以下の点に注意が必要です。
事業所の特性や対象となる利用者様の状況を踏まえ、最適な様式を選択することで、より効果的なアセスメントが可能となります。
- 厚生労働省が定める課題分析標準項目を全て網羅している
- 利用者様へのサービス提供形態(居宅・施設)に適した様式を検討する
- 記入項目の多さと業務効率のバランス、多職種との情報共有のしやすさを考慮する
アセスメントシートの記入方法と具体例
アセスメントシートの記入は、シートを埋めることが目的ではなく、作成後に適切なケアプランを作成するために作成します。
利用者様の状態によって記入方法や着目すべきポイントが異なるため、以下の具体的な記入例を参考にしてください。
アセスメントシートの書き方の基本
アセスメントシートには、客観的な事実とご本人・ご家族からの主観的な情報を区別して記載します。
情報は時系列で整理し、多職種からの情報も漏れなく記載することが重要です。
特に医療情報やADL、生活歴については、ケアプラン作成に直結する重要な情報です。
記入例①:脳梗塞の後遺症がある方
脳梗塞の後遺症がある方のアセスメントはADLに着目するのが大切です。
理由はどの程度体の機能が残っているかで、必要な援助内容が変わるからです。
右片麻痺があり移動には車椅子が必要。食事は自助具を使用すれば自分で食べられる。
記入例②:独居の方
独居の方は、ご家族だけでなく、社会福祉士との関わりとして、近所の方の支援をどの程度受けられるのかに着目します。
キーパーソンの息子は就労があるため、平日の介護は困難だが、金曜と土曜の夜は泊まり込んでいる。また、隣家の住民が週に1度は様子を見に来てくれている。
記入例③:認知症の方
認知症のある方の場合、認知症の症状の程度はもちろん、介護者にどの程度負担がかかっているかも確認が必要です。
アルツハイマー型認知症による被害妄想があり「嫁にお金を取られた」「ご飯を食べさせてもらえない」といった訴えがある。
嫁は訴えの対象になってしまうことに疲弊しているため、レスパイト目的でショートステイの利用が必要。
記入例④:慢性心不全のある方
心不全の方の場合は食事や水分量に制限のある場合が少なくありません。医師の指示と、異常がある際の対応を確認します。
心不全により労作時の息切れや下腿に浮腫がある。医師からは塩分6gの制限と、水分は一日1,000ccまでと指示が出ている。緊急時は●●病院へ相談。
記入例⑤:看取り期の方
看取り期の方の場合は、現在の状況と利用者様本人やご家族の意向を把握する必要があります。残された時間をどのように過ごしたいのか、意向に合わせた対応ができるよう体制を整えます。
十分長生きしたので痛いことはしたくない(ご本人)
痛みや苦痛をできるだけ取り除いてほしい(ご家族)
注意すべきポイントと記入時のコツ
アセスメント記入時は、以下の点に注意が必要です。
- 利用者様とご家族の意向をていねいに聞き取る
- 医療情報は正確に記載する
また、課題を設定する際の優先順位は以下のように考えます。
- 生命に関わる医療ニーズ
- 事故対策のようなリスク管理
- ADLの維持・改善
- 生活の質の向上
利用者様の状態や意向は変化することがあるため、定期的に見直すことも大切です。
アセスメントの手法と進め方
ここでは、ケアマネジャーがおこなうアセスメントの手法と進め方、アセスメント時に役立つヒントについて解説します。
主なアセスメント手法
ケアマネジャーがおこなう主なアセスメントの手法として「基本ケア」と「疾患別ケア」をご紹介します。
| 基本ケア | 全ての利用者に共通して「想定される支援」のことで、多職種との情報共有に必要な視点、必要な支援内容のこと。 心身の状況や利用者様ご家族の意向、緊急時の対応など、日常的におこなう支援のこと。 |
| 疾患別ケア | 疾患に特有な検討の視点あるいは可能性が想定される支援内容。 認知症、脳血管疾患、大腿骨頸部骨折、心疾患、誤嚥性肺炎などの疾患ごとにアセスメントする内容を示している。 |
アセスメントの際は、利用者様のADLや身体機能だけでなく、あらゆる視点からの情報収集をおこないます。
面談では、「食事はとれていますか?」といった単純な質問ではなく、「食事はいつ頃とっていますか?」「食事ではどのような動作がやりづらくなりましたか?」など、具体的に掘り下げて聞くことでより詳細な生活状況を把握します。
ステップごとの進め方:情報収集から課題整理まで
アセスメントは、事前準備から課題整理まで、段階的に進めていきます。
1.情報収集
訪問前に、病院や地域包括支援センターなどから事前に必要な情報を収集し、訪問時は利用者様やご家族の意向をていねいに聞き取ります。
2.課題整理
面談では、利用者様の基本情報からこれまでの人生について情報収集をおこない、収集した情報を分析して解決すべき課題を明確にします。
3.目標設定
利用者様やご家族へ、生活に関する意向を聞き取り目標を設定します。
アセスメントは1回で完了するものではなく、継続的なプロセスとして捉えることが重要です。
アセスメント時に役立つヒント
アセスメントには、利用者様の生活全般の把握が不可欠な一方で、病気や家計などのデリケートな内容は、信頼できない相手には話しづらいこともあります。
そのため、利用者様との良好な関係を築くことを意識することが大切です。
また、長時間の面談は相手に負担をかけるため、訪問は原則1時間以内に収めるようにします。
アセスメントにおける目標設定のポイント
アセスメントでは、生活課題を解決するための目標設定も必要です。
ここでは、目標設定の重要性とモニタリングとの関連性、具体的な記載方法について解説します。
目標設定の重要性
ケアプランに目標を明記し、チーム全体で共有することで、利用者様への適切なサービスにつながります。
たとえば「安全にお風呂に入る」という漠然とした希望を、「3ヵ月後には手すりを使って自力で浴槽に入れるようになる」といった具体的な目標に落とし込みます。
そうすることで、現状と目標の違いを把握でき、評価もしやすいケアプランになります。
具体的な目標を設定するためには、アセスメントの段階で利用者様の現状を把握し、サービスを利用するとどうなるのかを見極める力が必要です。
モニタリングとの関連性
アセスメントと似た工程に「モニタリング」があります。
アセスメントは、利用者様の状態や環境を分析し、課題を明確にする過程です。
一方、モニタリングはサービスの利用中や利用後に、目標の達成状況を定期的に確認する作業です。
居宅介護支援事業所の場合は、月に一度のモニタリングでサービス利用状況や目標達成に向けた進捗状況を確認します。
施設の場合、短期目標はおおむね3ヵ月、長期目標は6ヵ月を目安に評価を実施し、目標の達成状況に応じて支援内容を調整します。
目標設定の記入例とガイドラインに沿った記載方法
厚生労働省の課題分析標準項目に基づき、具体的な数値目標を含めた記載を心がけます。
特に優先度の高い課題から順に、実現可能な短期目標と長期目標を設定していきます。
記入例①:脳梗塞の後遺症がある方
ニーズ:脳梗塞の後遺症により右片麻痺があるが、杖を使って好きなものを買いに行きたい
長期目標(6ヵ月):週3回は自力で近所の商店まで買い物に行けるようになる
短期目標(3ヵ月):手すりを使用して自力で階段の昇り降りができる
記入例②:独居の方
ニーズ:独居だが身の回りのことは自立している。近所の人と交流を持ちたいとは思っているが億劫でなかなか外出できていない。「近所の人と交流を持ちたい」(ご本人)
長期目標(6ヵ月):近隣住民との関係を構築しながら、安心して在宅生活を継続できる。
短期目標(3ヵ月):地域のサロン活動に定期的に参加する
記入例③:認知症のある方
ニーズ:徘徊や介護拒否といった認知症の周辺症状によりご家族の介護負担が大きくなりつつある。「介護は続けたいがたまには休みたいときもある」(ご家族)
長期目標(6ヵ月):ご本人、ご家族ともに健康的で安全に在宅生活を継続できる
短期目標(3ヵ月):デイサービスやショートステイを利用し、家族がリフレッシュできる時間を確保できている
アセスメントでの注意点
アセスメントを効果的に実施するためには、利用者様本位の視点を常に持ち続けることが重要です。
また、記録の正確性を確保しながら、専門職としての質の高い支援を実現することが求められます。
利用者様の自己決定権と尊厳を守るためのポイント
利用者様の意思決定を支援する際は、ご本人の希望を最優先としながらも、専門職としての判断とのバランスを取ることが重要です。
特に認知症のある方や意思表示が困難な方の場合は、表情やしぐさなどの非言語的な表現にも注目し、日常生活での様子を丁寧に観察します。
また、ご家族の意向と本人の希望が異なる場合は、双方の立場を理解しながら、最善の方法を探っていきます。
アセスメントシート記入時の細かな注意点と成功事例
アセスメントシートには「本人が歩行に不安を感じている」といった主観的情報と、「手すりを使用して自力歩行が可能」などの客観的事実を明確に区別して記載します。
医療情報は主治医からの情報を正確に転記し、服薬内容や留意事項は漏れなく記録します。
また、多職種との情報共有では、専門用語の使用を適切におこない、誰が見ても理解できる記載を心がけましょう。
アセスメントの質を高めるための具体的なコツ
質の高いアセスメントを実現するには、質問と傾聴の技術を活用し、利用者様やご家族から必要な情報を自然に引き出すことが大切です。
また、生活環境や身体状況の観察は、ケアマネジャーだけの視点だけでなく、看護師やリハビリといった各専門職の意見も聴きながら、多角的な視点でおこないます。
記録は一貫性のある表現を使用し、定期的な振り返りを通じて自己の支援の質を高めていくことが重要です。
まとめ
ケアマネジャーがおこなうアセスメントは、利用者様の状態を正確に把握し、適切なケアプランを作成するための重要な過程です。
本記事を参考に、自信を持ってアセスメントに臨めると良いでしょう。
ケア人材バンクでは、ケアマネジャーや相談員、障がい福祉に関する求人を多数扱っています。
無料でご利用いただけますのでお気軽にご登録ください。
※当サイトで提供される情報は、一般的な情報提供のみを目的としており、専門家による助言に代わるものではありません。特定の状況に関するアドバイスや支援が必要な場合は、必ず専門家にご相談ください。