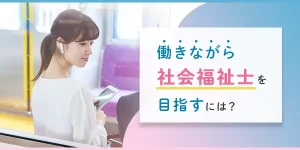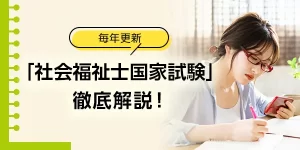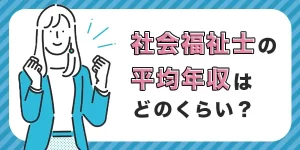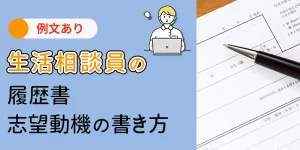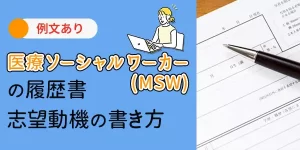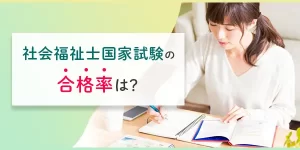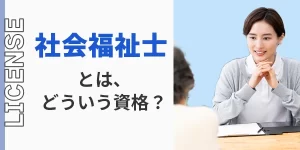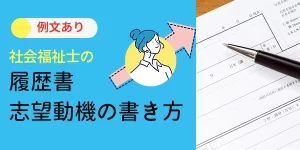社会福祉士は相談支援を行う専門職であり、精神的に大きな負担を抱えることが少なくありません。
本記事では、社会福祉士のストレスの主な原因や影響、そして効果的な対処法やメンタルケアのポイントを解説します。
ストレスに適切に対処し、自身でメンタルケアを行っていく方法を考えましょう。
目次
社会福祉士が直面するストレスの主な原因
社会福祉士が抱えるストレスや悩みは様々です。ストレスの原因となる主な原因を紹介します。
業務の多忙さと時間的なプレッシャー
社会福祉士の業務は多岐にわたっています。
一例ですが、以下のようなものがあります。
- 相談支援(電話、来所、訪問など)
- 行政手続きの支援
- 関係機関との連絡調整
- 記録・書類作成

解決が困難なケースでは、対応が長期化する場合もあります。
人手不足により、一人が担当するケースが増加している職場もあるでしょう。
また緊急性の高い案件の場合、他の仕事よりも優先して対応をすることもあり、時間外での勤務となる場面も少なくありません。
勤める施設の形態によっては夜勤があるなど、そもそも勤務が不規則な場合もあります。
緊張感の高さや長時間労働の負担はストレスの大きな原因となっています。
クライアントとの関係の中での疲弊
クライアントの中には、怒りや不安、敵意や拒絶などを表す人もいます。
割り切って業務にあたることができればよいのですが、繰り返し対応するうちに、否定的な言葉を真に受けて疲弊してしまう場合もあります。
また、一生懸命にクライアントと向き合うあまりに、社会福祉士の方も感情移入しすぎてしまい、プライベートの時間でも仕事のことを考えてしまうといったことがあります。
感情労働に対しての負担
社会福祉士の仕事は「感情労働」と呼ばれ、クライアントのために自身の感情をコントロールしながら対応する必要があります。
クライアントに否定的な言動をとられた場合でも、社会福祉士はクライアントに怒りをぶつけるのではなく、そうした気持ちをコントロールし、相手の言動に耳を傾けなければなりません。
こうした感情労働は、精神的・情緒的に疲労感を伴い、バーンアウト(燃え尽き症候群)やうつ病などのリスクになると言われています。
ストレスが社会福祉士に与える影響とは
メンタルヘルスへの影響
社会福祉士が仕事の中で受けるメンタルヘルスへの影響には以下のようなものがあります。
クライアントの悩みや課題に寄り添い、共感するうちに、支援する社会福祉士自身も同じように苦しみを味わい、精神的な疲労が蓄積してしまいます。
社会福祉士は、人の役に立ちたいという気持ちの強い人が多く、理想と現実のギャップから無力感、不全感を抱き、心が疲れ果ててしまうこともあります。
ストレスが長引くと、心を守るための防衛反応として、共感力が低下し、何を聞いても何も感じなくなり、仕事に対して冷めた態度になってしまうことがあります。

これらが続くと、仕事への意欲が低下し、心身の不調から長期休職・離職に至ってしまう場合もあります。
それがさらなる人手不足や業務の過多を招き、クライアントへの支援の質や職場の運営効率が低下してしまいます。
業務パフォーマンス低下のリスク
社会福祉士がストレスを受けることにより、業務パフォーマンスが低下することがあります。
具体的には、以下のようなものがあります。
社会福祉士の業務では、支援の方向性を決定したり、今後の処遇や対応を判断したりする場面があります。
ストレスが蓄積した状態では、認知機能が低下し、的確な判断が難しくなってしまいます。
社会福祉士はクライアントとの関係を構築し、他の専門職と連携して支援をしていくことが必要です。
ストレスが高まると感情のコントロールが難しくなり、クライアントへの共感性が低下し、チームワークが悪化してしまうリスクがあります。
ストレスがかかると、疲労や集中力、業務の遂行スピードが低下し、ミスが増えるといった影響があります。
作業効率が低下すると、業務負担はさらに増え、悪循環を引き起こしてしまいます。
ストレスを軽減するためにできること
時間管理や優先順位付けの重要性
社会福祉士の業務は多岐にわたるうえに、緊急の対応や不測の事態などにも柔軟な対応が求められます。
そのため、効果的な時間管理と優先順位付けを行うことが重要です。
時間管理のためにできる工夫には以下のものがあります。
やらなければならないタスクがたくさんあると、何から手を付けていいのか分からなくなります。
膨大なタスクの中で優先順位の高いものから取り組んでいきましょう。
クライアントの対応や訪問の予定に追われると、記録や事務作業をする時間が確保できなくなってしまいます。
そのような時は、あえて記録や事務作業を行う時間を予定として確保し、他の予定をブロックすることで、集中して記録に取り組む時間ができます。
記録や書類の作業は、毎回何を書くか考えながら書いていると時間がかかってしまうため、文書のテンプレートを作成しておくこともおすすめです。
作成時間を短縮するとともに、必要な事項の記載漏れを防ぐ効果もあります。
事業所によっては情報共有にチャットアプリやスケジュール管理アプリを活用しているところもあるようです。
こうしたツールを活用することで効率化を図れます。
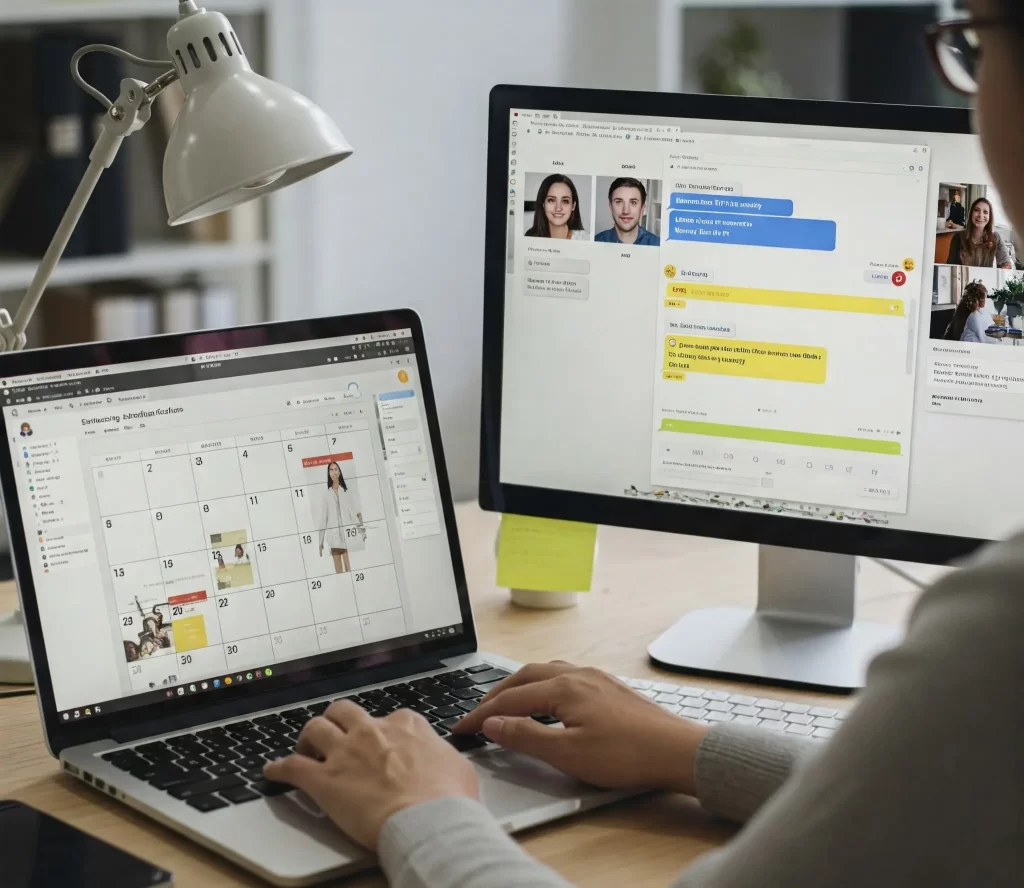
チーム内のサポート体制の強化
社会福祉士の行う相談業務は、正解がなく、対応や判断に迷うこともあります。
業務の多忙さも重なり、それぞれの担当者が業務を抱え込むと、孤立してしまいます。
そうしたことを予防するためには職場や、クライアントに関わるチーム全体で話し合いながら支援を進めていくことが有効です。
具体的には以下のようなものがあります。
職場であれば、定期的にミーティングなどで対応の進捗を共有し、支援が行き詰まった際には相談ができる場面を設けておくとよいでしょう。
多職種で連携して関わる場合は、カンファレンスを開催し、一人の担当者だけに負担が偏ることがないよう、チーム全体で方針を共有したり、方向性を考えたりすることが有効です。
チームで対応する場合は、役割分担することで各担当者の負担が軽減します。
たとえば、対象となる本人と家族、それぞれに課題がある場合は、本人の支援者だけではなく、家族に関わる支援者と連携していくことで、支援の質が深まります。
また、チームにさまざまな専門性をもった職員がいる場合は、それぞれの専門領域や得意な領域を活かして役割分担することも負担軽減につながります。
バーンアウトを防ぐには、スーパービジョンが有効です。
スーパービジョンを受けることで専門性が磨かれ、支援に行き詰まった場合でも、安心して対応に当たることができます。
職場によってはスーパーバイザーがいないといったこともあるかも知れません。
その場合は、同僚とのピアスーパービジョンも効果的です。
スーパービジョンとは…経験の浅い職員(スーパーバイジー)が経験の豊富な職員や管理責任者(スーパーバイザー)に助言や指導を受けることです。
メンタルヘルスを守るためのセルフケアの方法
ストレスマネジメントの基本
ストレスと上手に付き合うことを「ストレスマネジメント」と言います。
ストレスには原因(ストレッサー)と、それに対する心身の反応や行動があります。
ストレスマネジメントを行うには、自分自身の現在の状態を観察し、ストレスの原因や反応、気持ちに気づくことが大切です。
ストレスの原因には以下のものがあります。
- 物理的な原因:暑さ・寒さなどの気候、天候、騒音、有害物質など
- 生理的な原因:睡眠不足、体調不良、病気、空腹など
- 心理的・社会的な原因:人間関係、仕事のプレッシャー、役割の曖昧さ、業務過多など
ストレス反応にはいくつかの種類があります。
- 身体的反応:倦怠感、疲労、肩こり、めまい、不眠、食欲不振、頭痛、体重の増減など
- 心理的反応:イライラ、集中力の低下、不安、不満、落ち込み、物忘れ、無力感、絶望感、無気力など
- 行動:過食、飲酒、生活の乱れ、暴言、作業能力低下、ミスが増える、遅刻や欠席など
こうした症状がサインとなってストレスに気づくことができます。
また、事業所の規模によってはストレスチェックが義務付けられています。
年に一度検査があり、希望すれば産業医等と面接することもできるので活用しましょう。
休養のとり方やリフレッシュ方法
ストレスに気づくとともに大切なのが、ストレスに適切に対処すること(ストレスコーピング)です。
代表的なストレスコーピングには、以下のようなものがあります。
- 規則正しい生活と十分な睡眠
- バランスの取れた食事
- 適度な運動
- 友人や同僚、家族などに気持ちを話す
- ストレスの原因を取り除く・解決する
- 趣味などの好きなことをしてリフレッシュする
日頃、自身がどのようなストレスコーピングを行っているのか知り、自分に合ったコーピングを選ぶことが大切です。
社会福祉士が楽になる考え方のヒント
ストレスコーピングの一つに自分の考え方を変えることがあります。
物事の捉え方が変わると、気持ちが楽になり、前向きに仕事に取り組むことができます。
たとえば、担当しているクライアントの支援が膠着している場合であっても、日常の細やかな変化に目を向けて、肯定的に評価するようにしましょう。
クライアントが否定的な感情を向けてきた場合も、社会福祉士個人への批判ではなく、クライアントが感情転移(過去に体験した感情を支援者に向けること)を起こしている可能性や、自分自身がクライアントに感情を移入しすぎている可能性を念頭に入れておきましょう。
クライアントに関心を向けつつも、適度な距離を保ち、冷静で客観的な態度で振る舞うことを心がけましょう。仕事とプライベートをしっかり切り分けることも大切です。
まとめ
社会福祉士の仕事をしている人は、人の役に立ちたいという思いが強く、繊細で真面目な人が多いため、ついつい仕事にのめりこんでしまいます。
そこに業務の多忙さやストレスが加わると、心身に負担を生じることがあります。
常に自分を見つめながら適切な方法でストレスをコントロールし、職場の環境を整えるなど、適宜対策し、ストレスとうまく付き合いながら働いていくことが大切です。
思い切って働く環境を変えることが必要となる場面もあるでしょう。
ケア人材バンクでは社会福祉士の資格を活かせる相談員の転職情報も紹介しています。社会福祉士の転職先をお探しの際には、ぜひご活用ください。