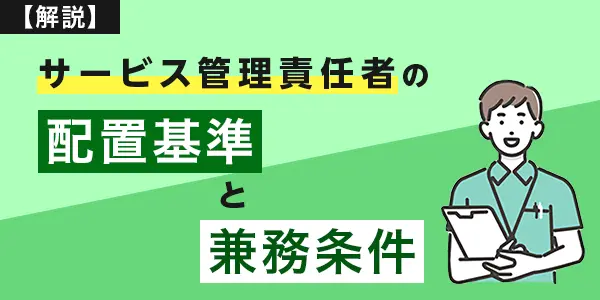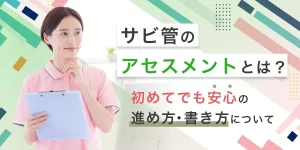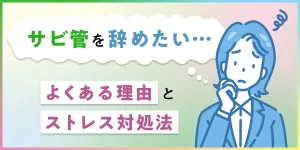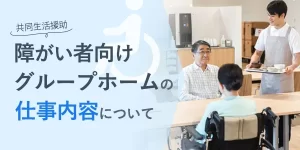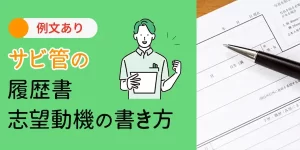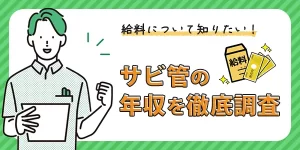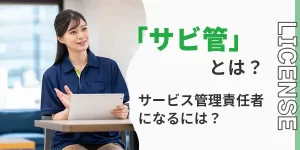サービス管理責任者(サビ管)は、障がい福祉サービスを提供する事業所において配置が義務付けられている職種です。
サビ管の配置基準は提供しているサービスによって異なり、また兼務の可否についても同様です。
本記事ではサービス管理責任者の配置基準や他の職種との兼務の可否について紹介します。
配置基準や兼務について詳しく知りたい人は参考にしてみてください。
※本情報は厚生労働省、自治体HPを参考にしていますが、最新の情報は、必ず各自治体の公式HPをご確認ください。
目次
サービス管理責任者の配置基準
障害者総合支援法により、障がい福祉サービスを提供する事業所には「サービス管理責任者(サビ管)」の配置が義務付けられています。
配置の基準はみな同じではなく、提供しているサービスによって異なります。
まずはサビ管の配置基準について紹介していきます。
サビ管の配置基準の役割
サービス管理責任者の配置基準は以下のようになっています。
| 日中活動系事業所 (療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援など) | 利用者60人に対して1人の配置 |
| 共同生活援助 | 利用者30人に対して1人の配置 |
日中活動系は利用者60人に対してサビ管1人ですが、共同生活援助では利用者30人に対してサビ管1人の配置となっており、サービスによって差があることがわかります。
サビ管は、利用者の個別支援計画の作成や計画作成に必要な会議の実施、職員への助言や指導、関係機関との連絡調整などの業務を行います。
サービス提供における責任を追う立場であり、利用者に必要なサービスが提供されるように事業所の中心となって動くリーダー的なポジションです。
サビ管の配置が義務付けられることでサービスの安定、質の向上に繋がっています。
2人目のサビ管配置が可能な条件
質の高いサービス提供体制を構築するため、複数のサビ管を配置することが推奨される場合があります。2人目のサビ管を配置するための要件は以下の通りです。
- 基礎研修の修了: 「基礎研修」を修了した段階で、既に実践研修を修了した1人目のサビ管が配置されている事業所において、2人目のサビ管として配置することが可能になります。
- 届出: 2人目のサビ管として配置する場合、管轄の指定権者(都道府県や市町村)への届出が必要です。
- 業務範囲: 基礎研修修了者である2人目のサビ管は、個別支援計画の「原案」を作成することができます。
※ただし、最終的な個別支援計画の決定・管理は、実践研修を修了したサビ管が行う必要があります。 - 実践研修の受講: 基礎研修修了後、一定期間の実務経験(OJT)を経て「実践研修」を修了することで、正式なサビ管として1人で業務を行えるようになります。
ポイント: 2人目のサビ管は、あくまで実践研修修了者の指導・監督のもとで業務を行う位置づけであり、単独でサビ管としての業務を完結させることはできません。
出典:サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者 になるまでの流れ
サビ管のみなし配置とは
「みなし配置」とは、特定の要件を満たす場合に、実践研修を修了していない者でも一時的にサビ管として配置できる経過措置や特例措置のことです。
(1) 研修制度移行に伴う経過措置
過去、サビ管の研修体系が変更された際、新しい研修(基礎研修+実践研修)への移行期間中にサビ管の確保が困難になることを避けるため、旧体系の要件を満たす者や、新体系の基礎研修を早期(令和元年度~3年度)に修了した者を対象とした「みなし配置」の経過措置が設けられました。
これらの方々は、基礎研修修了後3年以内に実践研修を修了する必要がありました。
現在は限定的な範囲にとどまっています。
2025年4月現在では、この当初の経過措置の対象期間(基礎研修修了後3年)は多くのケースで終了していると考えられます。
(2) サビ管欠員時の特例措置(令和5年度改正)
現在、より重要な「みなし配置」の規定は、サビ管が「やむを得ない事由」により欠員した場合の特例措置です。
これは令和5年度の報酬改定・制度改正で明確化・要件整理されました。
- 目的: 予期せぬ理由(急な退職、病気療養など)でサビ管が不在となり、事業所運営に支障が出ることを防ぐための措置です。
- 期間: 要件を満たす場合、最長2年間、実践研修未修了者をサビ管と「みなして」配置することが可能です。
- 要件: この特例的な「みなし配置」を行うためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
- 配置される予定の者が、サビ管としての実務経験要件を満たしていること。
- その者が、サビ管が欠員となる以前から当該事業所に(他の職種等で)配置されていること。
- サビ管が欠員となった時点で、その者が既に基礎研修を修了していること。
- 義務: みなし配置の期間中(最長2年以内)に、当該者は実践研修を受講・修了し、正式なサビ管として配置される必要があります。
- 届出: この措置を利用する場合も、管轄の指定権者への届出が必要です。
- ポイント: 「やむを得ない事由」によるみなし配置は、あくまで緊急避難的な措置であり、計画的な人員配置の代替とはなりません。期間内に実践研修を修了し、正規の配置に戻すことが前提となります。
出典:サービス管理責任者等研修制度について(厚生労働省)
出典:サービス管理責任者等の要件に特例が認められる場合(大阪府)
サビ管の配置基準を満たさないとどうなる?
サービス管理責任者は、障害福祉サービス事業所における人員配置基準において必須とされる職種です。
この基準を満たさない場合、以下のような行政処分やペナルティを受ける可能性があります。
- 行政指導・改善勧告: まず、指定権者(都道府県や市町村)から、基準を満たすよう指導や改善勧告が行われます。
期限までに改善が見られない場合、より重い処分に進む可能性があります。 - 報酬減算: サビ管が不在または基準数を満たさない状態が続くと、「人員欠如減算」として、事業所が受け取る介護給付費等が減額される可能性があります。
これは事業所の経営に直接的な影響を与えます。 - 新規利用者の受け入れ停止: 悪質な場合や改善が見られない場合、新規利用者の受け入れを一時的に停止するよう命じられることがあります。
- 指定の効力停止(一部または全部): さらに重大な違反と判断された場合、一定期間、事業所としてのサービス提供ができなくなる「指定の効力停止」処分を受ける可能性があります。
- 指定取消: 最も重い処分として、事業所の指定そのものが取り消される可能性があります。
これは事実上の事業廃止を意味します。
サビ管の適正な配置は、法令遵守の観点からも、質の高いサービス提供を維持する観点からも極めて重要です。基準を満たせない状況が発生した場合は、速やかに指定権者に相談し、適切な対応をとる必要があります。
サビ管の配置基準を満たさないとどうなる?
サビ管が一定期間配置されておらず、配置基準を満たせていないと欠如減算が適応されます。
欠如減算が適応されると、サビ管が不在となった月の翌々月から人員欠如が解消されるまでの間、基本報酬の3割が減算され、5か月目以降は5割の減算となります。
事業所が得られる収入が減り、事業所運営に大きな影響を与えてしまう他、悪質な場合には指定の取り消しになる可能性があります。配置基準を満たせるように事業所として体制を整えることが大切です。
サビ管の転職相談受付中
サビ管の転職サポートに登録(完全無料)サービス管理責任者が兼務できる業務は?
サビ管は他の職種と兼務をすることができますが、全ての職種と兼務できるわけではありません。
ここからはサビ管が兼務できる職種について紹介します。
サビ管兼務の判定基準
サビ管の兼務は日中系事業所、グループホーム、多機能型で違いがあります。
また、事業内だけでなく、事業間においても違いがあります。
| サビ管と管理者の兼務 | サビ管と直接処遇職員との兼務 | |
|---|---|---|
| 日中活動系の事業所 | 可能 | 不可 *ただし、2人目のサビ管の場合兼務可能。 |
| グループホーム | 可能 | 可能 |
| 多機能型事業所 | 利用者数60人以下の範囲で可能 | 不可 |
次に、事業所間の兼務について例を紹介します。
同じグループホーム内で「管理者」と「サービス管理責任者」の兼務をしている場合、他のグループホームの「管理者」や「サービス管理責任者」の兼務はできませんが、他のグループホームの「直接処遇職員」との兼務は可能です。
サービス管理責任者が、2つのグループホームの「管理者」を兼務することはできません。
ただし、グループホームの利用者数が20 人未満の場合に限り、グループホームの「サービス管理責任者」と日中活動系の「管理者」との兼務が可能です。
日中活動系の「管理者」「サービス管理責任者」を兼務している場合、両事業所の合計利用者数が、1/2人のサービス管理責任者で対応可能な人数以内の場合に限り、グループホームの「サービス管理責任者」との兼務が可能です。
日中活動系の「管理者」「サービス管理責任者」を兼務している場合、グループホームの「直接処遇職員」との兼務はできません。
ここで紹介した以外にも個別の事例があるため、詳しく知りたい場合には各地域の担当窓口にご確認ください。
サビ管が兼務できる仕事
施設管理者
サビ管は施設の管理者との兼務が可能です。
管理者は事業所のトップであり、職員の確保や配置、請求管理、備品や消耗品等の管理など事業所全体の管理を行います。
サビ管と兼務する場合には、サビ管の業務に加え、上記の管理者の業務も行います。
直接処遇職員
直接処遇職員は、利用者の支援に直接従事している人のことです。
常勤・非常勤は問いません。
具体例を挙げると世話人や生活支援員、就労支援員、ホームヘルパー等の職種が該当します。
日中活動系事業所のサビ管は、直接処遇職員との兼務をすることはできませんが、共同生活援助のサビ管は兼務が可能です。
多機能型の場合、多機能型事業所の利用者数60人以下の範囲であれば、管理者とサービス管理責任者は兼務が可能です。
施設別のサビ管兼務
生活介護・療養介護
生活介護・療養介護でのサビ管の兼務可否は以下の通りとなります。
- 管理者兼務:〇
- 直接処遇職員:×
※ただし、2人目サビ管はこの限りではありません
障がい者支援施設などで主に昼間において、入浴・排せつ・食事等の介護、生活等に関する相談・助言、創作的活動・生産活動の機会の提供等のサービスを行う通所型の事業所です。
病院等に入院している医療と常時介護を必要とする障がいのある方に対して、主に昼間において、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行うサービスです。
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立訓練(機能訓練・生活訓練)でのサビ管の兼務可否は以下の通りとなります。
- 管理者兼務:〇
- 直接処遇職員:×
※ただし、2人目サビ管はこの限りではありません
身体障がい・難病のある方などに対して、障がい者支援施設、障がい福祉サービス事業所または障がいのある方の居宅で、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーション、生活等に関する相談および助言などの支援を行います。
入所施設・病院を退所・退院、特別支援学校を卒業した方等に対して、障がい者支援施設、障がい福祉サービス事業所または障がいのある方の居宅において、入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談および助言などの支援を行います。
共同生活援助(共同生活介護)・宿泊型自立訓練
グループホームのサビ管の兼務可否は以下の通りとなります。
- 管理者兼務:〇
- 直接処遇職員:〇
主として夜間において、共同生活を営むべき住居で相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行うサービスです。「グループホーム」とも言われます。
※共同生活介護は、現在は共同生活援助に一元化されています。
知的障がいまたは精神障がいのある方に対して、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行うサービスです。
また、サビ管と管理者を1つのグループホームで兼務している場合、他のグループホームの管理者やサビ管を兼務することはできませんが、直接支援員は兼務することができます。
就労移行支援・就労継続支援
就労移行支援・就労継続支援でのサビ管の兼務可否は以下の通りとなります。
- 管理者兼務:〇
- 直接処遇職員:×
※ただし、2人目サビ管はこの限りではありません
就労を希望する65歳未満の障がいのある方で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方に対して、生産活動、職場体験など活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談などをおこなうサービスです。
通常の事業所に雇用されることが困難な障がいのある方に対して、生産活動の機会提供や就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行うサービスです。
A型とB型の2つの種類があり、一番の違いは「雇用契約の有無」です。A型は雇用契約を結びますが、B型では結びません。
施設入所支援
施設入所支援でのサビ管の兼務可否は以下の通りとなります。
- 管理者兼務:〇
- 直接処遇職員:×
※ただし、2人目サビ管はこの限りではありません
施設に入所する障がいのある方に対して主に夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行うサービスです。
多機能型事業所
多機能型事業所でのサビ管の兼務可否は以下の通りとなります。
- 管理者兼務:〇
*ただし利用者数60名以下の場合 - 直接処遇職員:〇
※重度の障がい児に対応する利用者数20名以下の事業所の場合
一つの事業所において2つ以上の障がい福祉に関するサービスを行っている事業所です。
サビ管と児童発達支援管理責任者(児発管)は兼務できる?
児童発達支援管理責任者(児発管)は、障がい児を対象とした障がい福祉サービスを提供する事業所に配置が義務付けられている職種です。
主な業務は、個別支援計画の作成や関係機関との連絡調整などサビ管と同じようなものになります。
ここからは、サービス管理責任者と児童発達支援管理責任者は兼務することができるか紹介します。
サビ管と児発管を兼務する施設
多機能型として障がい福祉サービスと障がい児福祉サービスを提供している事業所ではサビ管と児発管を兼務することができます。
具体的には、以下のようなサービスを2つ以上提供している場合が多いです。
- 障がい福祉サービス
生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型 - 障がい児福祉サービス
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援
サビ管と児発管の兼務が発生するケース
サビ管と児発管の兼務が発生するケースとしては、多機能型としてサービスを提供していく際に「人員が足りない」「人件費を安くする」などの理由からサビ管と児発管を兼務し運営していくケースが考えられます。
また別の理由としては、兼務をすることで仕事の幅を広げ、スキルアップやキャリアアップを目的とするケースも考えられます。
兼務をすることは、業務量が増えて忙しくなる、負担が増えるというデメリットがある一方、視野が広がる、新しい経験ができるといったメリットもあります。
大変ではありますが、仕事の幅が広がることで人間として成長することにも繋がるでしょう。
よくある質問FAQ
まとめ
サービス管理責任者(サビ管)の配置基準、兼務について紹介しました。
サビ管は障がいのある人の生活を支える重要な役割のある仕事です。全国的に障がいのある人は増加傾向にあり、ニーズは高まっています。
「ケア人材バンク」には、障がい福祉専門の転職エージェントがおり、無料で転職支援サービスを行っています。サビ管として転職を考えている人はぜひご活用ください。
✨ 気になったらSNSシェア ✨
※当サイトの情報は、掲載時点での情報に基づいています。また、情報の正確性、最新性を保証するものではありません。